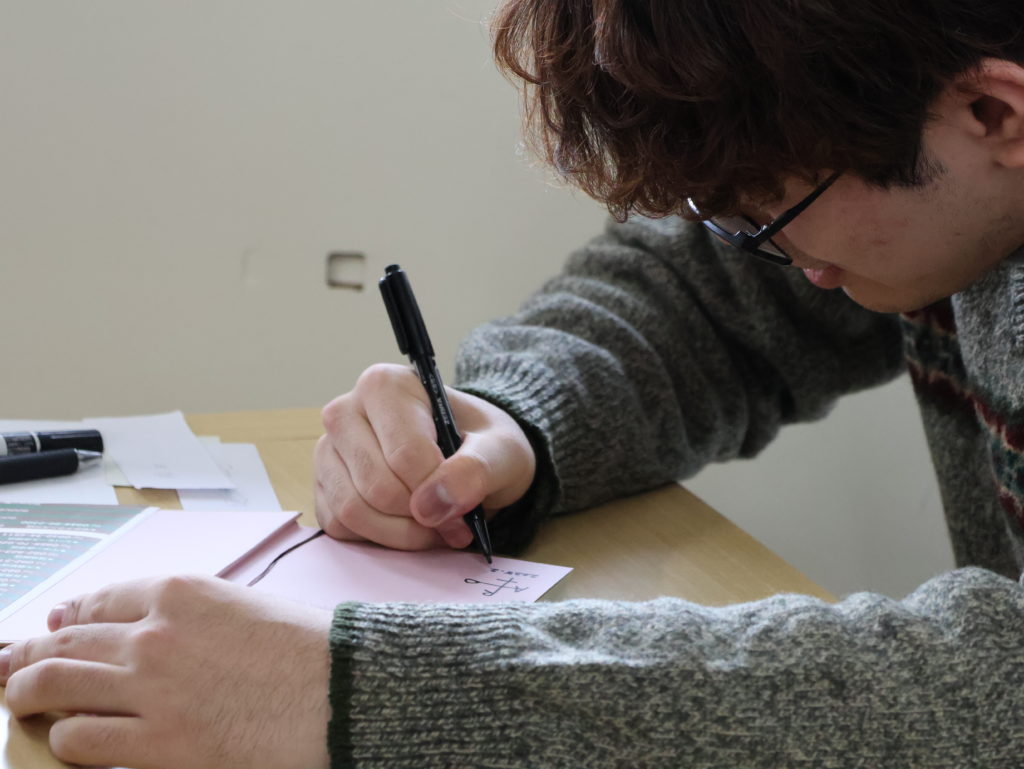西南学院大学大学院に在籍しながら弱冠23歳で芥川賞を受賞した鈴木結生さんは、日本バプテスト連盟日本バプテスト連盟郡山コスモス通りキリスト教会(福島県郡山市)で小学生時代を過ごした。受賞後、さまざまな媒体のインタビューでも、親が牧師だったことや、そうした環境で育ったことが創作活動にも多大な影響を及ぼしたことについて語っている。改めて受賞作が生まれた経緯、自身の信仰観などについて話を聞いた。
■ 一番遊びたい場所が教会だった
――いわゆる「2世」としての葛藤や、他の家庭と違うことへの違和感などはありませんでしたか?
鈴木 クリスチャンであるということが、僕の中では少し特別で、逆に嬉しかったような気もします。幼いころは、友だちをどんどん教会に誘って遊んでいました。あんなに広い遊び場所は他にないので、みんな喜んで来ていましたね。クラスでも少し中心的な位置にいたから、親が牧師だということが積極的に言えたという面も多少あるかもしれません。教会では他の子よりも多様なジャンルの大人と関わることがあったので、コミュニケーションの面でもうまく立ち回れたのだと思います。作家の先生方や人前でもあまり緊張せず、自然体で話せるのは、教会で育ったおかげかもしれません。聖書をはじめ子どものころから本には恵まれた環境でもあったので、絵本や劇にもたくさん触れることができました。
――日曜日に教会に行かなければならないとか、不自由さを感じたことはありませんでしたか?
鈴木 僕はまったく感じなかったですね。好きな人がいっぱいいる一番遊びたい場所が教会で、学校も楽しいけれど、一番じゃないという思いはずっとありました。子どもたちで勝手に礼拝ごっこをしてみたり、しおりを手作りして、バザーで教会員に売った収益から献金したり、そういうことが許される自由な雰囲気でした。子どもだけで自発的にどんどん活動できるのが楽しくて、学校では許されないいろいろな遊び方を、教会学校などを通して教えてもらいました。教会の大人たちにも、遊ぶのが上手な人たちが多くて、そういう環境を確保してくれたおかげだと思います。
――牧師家庭に生まれて良かったと感じている。
鈴木 そうですね。それがなかったら作家になることも芥川賞を受賞することもなかったと思います。西洋文学を好きになったのもこの環境のおかげだと思いますし、大学で文学を勉強する多くの人にとって、聖書を知らないというのが実は最初のつまずきだったりするんですよ。でも、自分は聖書を知っていたから、西洋文学に関心が向いて、そのまま探究していった先に今回のような作品を書けたという意味でも間違いなく影響は大きいです。
――震災を機に転居された当初、環境の変化に適応するのはたいへんではありませんでしたか?
鈴木 さすがに引っ越し直後はホームシック的な状態になって、それが初めて小説を書く動機にもなりました。3年生になるまでは、友だちと家を行き来して外で遊んだりすることも多く、もちろんひとり遊びをするのも好きだったのですが、震災を機に室内で遊ぶことが主になって、外出する頻度が極端に減りました。やっぱり原発の影響はとても大きかったですね。
■ 宗教を異質なものとしてではなく 当然あるものとして
――受賞作『ゲーテはすべてを言った』にも聖書、教会、神学、牧師の話題が頻出します。
鈴木 2025年3月号の文芸誌『文學界』(文藝春秋)に収録されたエッセイ「信仰と創作」でも書きましたが、僕が目にしてきたような普通のクリスチャン家庭を文学の世界に登場させてみたいという思いがあったんです。やはり文学が宗教を扱うと、「宗教2世」を含め、どうしても保守的、カルト的な描かれ方をしてしまう。そこには一定の必然性もあるとは思いますが、同時に自分が感じている感覚とは少しズレがあって、宗教のプラスの側面も描いていいはずだという思いはありました。ただ、それを前面に押し出すと一般的な評価が得られにくいというのも、クリスチャンとして生きてきてずっと感じていたので、表面的には学問の問題として打ち出した上で、登場する家庭の中にクリスチャン的な風土があるという設定にしてみました。作品の根底に信仰の問題があると見抜かれている方もいて、そういう指摘は批判にしろ、肯定にしろ、とても嬉しかったですね。
――むしろ意図的に入れ込んでいたということでしょうか?
鈴木 説得力があるかどうかで考えると、やっぱり宗教的な背景があるからこそ真剣に悩むと思うので、キャラクターの造形としても必然だと思いました。ある雑誌のインタビューで、クリスマスの描写について過剰じゃないかと聞かれたんですが、僕にとっては「普通にある」話なわけで(笑)。そこは、こちらのチューニングがズレていたと気づかされましたが、信者である〝こちら側〟の「普通」を異質なものとしてではなく、あえて当然あるものとして書くという意識はありました。逆に学問の世界について問題提起する上では、かえって読みやすい設定になった面もあると思っています。
*以下、ネタバレを含みます。
■ 不幸な人、毒をどう描くか
―― 一部では研究不正のモチーフが、実際に起きた深井智朗氏をめぐる一連の問題だったのではないかと指摘されています。
鈴木 構想していた当初はまったく知らず、書き始める前にネットニュースで少し知った程度でした。深井さんの本も読んでいません。ただ、この件は非常に小説的だなと。アカデミズムの視点から考えると、4年間この世界に身を置いてきた者として、自分にも同様の危険性があると感じました。アカデミックの装いで論文を書きながら、根底にある想像欲求のようなものから小説家を志し、今もアカデミックな書き方とクリエイティブな書き方の「あわい」を揺れているという実感がありますので、決して他人事ではないなと。
当初の設定では、捏造事件を起こす然(しかり)先生は半ばで退場するキャラクターだったんです。でも、そのシーンを書きながら辛くなってしまって、おそらく彼は実際に面白い人なのに、この一点だけで退場するのはどうなんだろうと。でも、今の時代の感覚としては絶対に退場しなければならない。そのリアリティは絶対揺らいではいけないと思い、ほとんど祈るような感じで悩んでいたんですが、最終的な落としどころを思いついた時には涙が出て、これで行けると確信しました。それまでは筆が進まず、書きながらとても苦しかったと記憶しています。
――不幸な道をたどる人物を登場させたくないという思いがあるのでしょうか?
鈴木 そこは自分の弱点だと自覚していて、今回の作品にもあまり不幸な人、弱い人が出てきません。本当はそういう人物も書けるようにならないといけないと思っています。アメリカ文学を代表するカート・ヴォネガットが、「お前の小説には悪い人間が出てこない」と父に言われてショックを受けたという逸話を読んで、自分もそうだと思った村上春樹が『ねじまき鳥クロニクル』を書いたとされています。一方で村上は早稲田大学時代、小津安二郎の映画を好んで見ていて、その理由を「小津作品には悪い人が出てこないから」とも書いています。本人は文学的に自分を成長させるため、あえて悪を書こうとしたという点に共感しました。
ただ、今回は自分の作品に不幸な人を出したくないというよりも、愛着のある然先生との個人的な対話の結果、彼が書き手を超えて語ってくれた瞬間がありました。せっかくキャラクターとして成長してくれたのに、それをある意味、作家の権限で捏造だったということにして退場させるというのは、あまりに都合が良すぎると考えた結果です。
――芥川賞選考委員の川上弘美さんが選評の中で、「統一(とういち)さんが、いい人すぎて、この小説自体には好感が持ててしかたないのですが、いい人は、少し苦手です」と書かれていました。
鈴木 確かに、そうだなと(笑)。川上さんはバシバシと本質を優しく突く感じがカッコいい。文章自体は柔らかい感じなのに、その柔らかさがバシッと決まっている。実は高校の担任からも「毒がまったくない」と言われたことがあって、なるほどと思いつつも、毒を作ろうと思って作る方が嘘をつくことになってしまうので、敬愛する大江健三郎が言うように、今のところ僕が思う「本当のこと」を書きたいと思っています。
――「無自覚なコンサバティブ」と評されることについてはいかがですか?
鈴木 クリスチャンであるということは、世界的に見たらかなり「コンサバ」ですが、日本ではマイノリティです。同じことを文学の世界でも感じていて、コンサバっぽいものも違う文脈に置くと、実は革新だったりするわけです。世界的に見た時に、宗教的なコンサバ性、あるいは僕の文学的なコンサバ性――例えばヨーロッパの男性作家しか読んでいないとか――は矯正した方がいいと思いますが、ただどうがんばっても批判がなくなることはないので、自分がその都度、ちゃんと祈りながら書けることを書いていきたいと思います。
――文藝春秋誌のインタビューで、「不安だらけの時代だからこそ、せめて文学には安心を求めたい」と答えておられました。
鈴木 島田雅彦さんがおっしゃっていて印象的だったんですが、社会が杓子定規になっている時には、文学はアウトサイダーとして多少エキセントリックなことをするけれど、社会がおかしくなった時には、文学者は常識を語らなければならないと。常に反体制であるということは、今の時代には逆に伝統的であるとも言えるわけで、ゲーテに関しても同じです。若い時はかなりロマン派的だったのに、晩年はどんどん古典主義に向かっていったというのは、ヨーロッパの揺れ動きという歴史的文脈を考える際にとても理解できます。
*全文は4月11日付本紙に掲載。電子版(PDF)は以下のnoteでも購読可能。
https://note.com/macchan1109/m/mc01613d1fac9
すずき・ゆうい 西南学院大大学院1年(英文学専攻)。2001年福岡県生まれ。日本バプテスト連盟郡山コスモス通りキリスト教会で幼少期を過ごす。震災を機に福岡へ転居。西南学院大学在学中の2024年、『人にはどれほどの本がいるか』で第10回林芙美子文学賞佳作を受賞しデビュー。同年、同大学大学院に進学、英文学を研究する。2025年、『ゲーテはすべてを言った』で第172回芥川龍之介賞を受賞した。