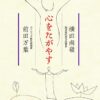寺院には地域ごとや宗派ごとなど、横のつながりがある。私が住職を務める地域では、5月や6月には同宗派の近隣寺院がお互いの法要へと出席し合う風習がある。その法要は「施餓鬼会(せがきえ)」といって、『救抜焔口餓鬼陀羅尼経』が出典として挙げられる。内容を見ると仏教のはじまりとなった人であるお釈迦さま、彼の弟子の一人が主人公だ。
阿難尊者という弟子が瞑想をしていると口から火を吐く餓鬼が現れて言う。「お前は3日後に死んで、俺と同じ餓鬼道に落ちる」。助かる方法を聞く阿難尊者に、餓鬼は重ねて言う。「すべての飢えたる餓鬼に飲食を施し供養せよ」。餓鬼の数は無辺のため無理難題である。そこで阿難尊者はお釈迦さまに教えを乞うのだ。お釈迦様は言う。「一椀の食物を供え、とある陀羅尼のお経を唱えて加持せよ。無量の食物となり、一切の餓鬼は空腹を満たされる。みなを救うこととなる」。弟子は教えに従うのだった。現代の僧侶もこの教えに従い、とある陀羅尼のお経を法要で読んでいる。
7月や8月には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」法要、通称お盆がある。『盂蘭盆経』が出典として挙げられ、こちらでは目蓮尊者が主人公である。彼は仏道修行により神通力を得て、今は亡き母親がどうしているか調べるのだ。餓鬼道にいることが分かるので、飲食を届けるのだが無駄に終わってしまう。自分ではどうにも救うことができず、目蓮尊者はお釈迦さまに教えを乞う。お釈迦様は言う。「修行を終えた修行者たちに、お盆に食べ物を乗せて供養をせよ。みなを救うこととなる」。弟子は教えに従うのだった。現代の日本人もこの教えに従い、僧侶や僧侶となった亡者にお膳を供える。
施餓鬼会とお盆は開催時期も近く、どちらも餓鬼救済の内容のために混同されやすいのだが、まったく違う。施餓鬼会は自分が餓鬼になり、お盆は自分の母親が餓鬼になる。「もしかしたら今は亡きあの人は苦しみの世界を抜け出せずにいるかもしれない」「この私が餓鬼になるなんて」
施餓鬼会の経典では、阿難尊者は過去の人が餓鬼になっていることを思い、なんとかしたいと仏道修行に励む。しかし「過去の人がなっているかもしれないと想定する餓鬼」の立場に、今度は現在の自分がなってしまう。この構造を考えると、阿難尊者が過去世代の人のことを思うように、未来世代の人が現在世代の人のことを思ってくれる関係性が浮かび上がってくる。もちろんその保証はないのだが。
施餓鬼会とは、過去につながる今からの視点同様に、今につながる未来からの視点を持ってみてはどうかと、現代を生きる私たちに与えてくれていると思うのだ。そこでさらに見方を展開していきたい。「幸せな人生を送っていらしたんだろうな、安寧でいらしたんだろうな」と未来世代から願われる、誓われる存在へと、私たちは目指せないものだろうか。どのような恵みを現代を生きるこの私はいただいてきたのかと、過去からの送りものを慮れないか。過去から現在未来へと流れる世の中の変化をも、自分のあり方をも肯定したい。さらには、バトンタッチされてきた恵みを現在から未来へと送り届けられるようにするにはどうすればよいだろうか、と。
仏教行事とは、「おれが、おれが」の気持ちを置いて、時間や空間を超えた視点、己を俯瞰して見る視点を持ってみせよと迫ってくるのである。

向井真人(臨済宗陽岳寺住職)
むかい・まひと 1985年東京都生まれ。大学卒業後、鎌倉にある臨済宗円覚寺の専門道場に掛搭。2010年より現職。2015年より毎年、お寺や仏教をテーマにしたボードゲームを製作。『檀家-DANKA-』『浄土双六ペーパークラフト』ほか多数。