ヘルマン・ヘッセ(一八七七~一九六二)と言えば『車輪の下』を思い浮かべる向きもあろうが、弱冠二九歳の所謂青春小説である。〈知⇔愛〉〈生⇔死〉〈聖⇔俗〉など二極の対立をテーマとした作風が大きく転換し、矢車のように中心から何本もの対立軸が伸びるようになり、更にそれが複雑に絡み合い、中心が移動し浮遊し始め、対立軸さえ曲線を描くまでになるのは、熟年を迎えた四十代以降のヘッセだと思う。ここではそうした深まりと拡がりを増す彼の精神世界を見ていきたい。
「私の信仰告白」と自ら記す『シッダールタ』(一九二二)は、仏陀の幼名ゴータマ・シッダールタに由来する。それ故釈迦の伝記と誤解されたりもするが、釈迦は別の人物ゴータマとして後段に登場するから、むしろヘッセの精神遍歴を最もよく語る作品と言える。
インドのカースト(身分制度)で最高位の僧侶階級バラモンの息子として生まれ、俊秀の誉れ高いシッダールタは、苦行僧の群れに無二の友ゴーヴィンダと共に加わり、自分探しの旅に出る。それは〈真我〉を、聖音〈オーム〉を求める巡礼であった。やがてゴータマと呼ばれる仏陀(覚醒者)と出逢うと、「あれを見よ! あの人こそ仏陀だ」と声をあげて、イエスを指すピラトを彷彿とさせるが、暫くすると「何びとも解脱は教えによっては得られない!……一人自分の目標に到達するため遍歴を続ける」と告げ、帰依したゴーヴィンダを残して仏陀のもとを去って行く。
途上彼は・私は自分について何も知らない。自我を細かく切り刻み、殻をはごうと欲したが、そのため自分自身は失われてしまった・と嘆く。こうして第一部は終わるのである。
いざ筆を執ると一気呵成に仕上げることの多いヘッセには珍しく、第二部を書き始めるまでにおよそ一年半の空白がある。精神を患う最初の妻マリアとの別居、息子達を余所に預けてのスイス移住、第一次世界大戦中に捕虜保護機関で慰問新聞の編集に携わり、反戦平和の論調が批判を浴び、世間の反感を買ったことを理由に上げることができよう。しかし何よりも、ヘッセ自身の思索が行き詰まったのだと思う。
第二部のシッダールタは一転して世俗にまみれる。川を渡った対岸で娼婦と交わり、大商人の庇護の下で財を築き、かつて蔑んでいた小市民的享楽を舐め尽くすが満足できる訳もなく、惨めに打ちひしがれ再び川に戻ってくる。
この作品には「渡し守」なる謎の人物が登場する。名をヴァズデーヴァと云う。言数少なくシッダールタに川に聴き川に学べと諭し、仏陀を超える師となるが、弟子の顔に流れに傾聴し身を委ねる悟りの境地を見て取ると、「光を放ちながら」静かに森の奥へと姿を消す。筆者は渡し守に、・Quo Vadis ?・(主よ何処へ?)と問うペトロを残して歩み去るキリストの背を見る想いがするのである。渡し守を継いだシッダールタの顔には、老いたヴァズデーヴァ、そして老ヘッセとも共通の深い哲学の皺が刻まれていて、今尚多くの人生を乗せて川を渡っているように思えてならない。
シッダールタが覗き込む川面は、自分の顔を映すと同時に、ありとあらゆる顔が流れ寄り流れ去る。全てが友であり師であり、苦楽、善悪、生死、あらゆる悩みと笑いが縺れ合い結び付き、形を変えて過ぎて行った。シッダールタは一つの声が川から立ち上るのを聴く。全てを融合する唯一の言「オーム(完成)」だった。
『ガラス玉演戯』
・ヘルマン・ヘッセ:著
・高橋健二:訳
・復刊ドットコム
・2004年刊
・四六判・並製 528頁
・3,080円
※ご紹介の本は現在入手が難しい可能性があり、図書館のご利用をお薦めいたします。尚、電子書籍の出版もあります。
ヘッセがノーベル文学賞(一九四六)を受賞する契機となった『ガラス玉演戯』(一九四三)は、最後の作品で長編の上に難解である。この演戯がいかなるものかは具体的に分かり難い。高度な法則で組み上げられた神秘の記号と言で、文芸・音楽・美術の総合芸術を、全ての科学、特に天文学や高等数学を表すらしいのだが、魔術性を帯びて色とりどりの様々な大きさと形のガラス片が音楽を奏で図形を描く。万華鏡のようでも、色ガラスの玉で記されているオーケストラの指揮者のスコア(総譜)のようでもある。
この時機ヘッセは妻の精神病に翻弄され、自らも精神療養をしてフロイトの精神分析の影響を受けた。多くの天才が統合失調症傾向にあったとされるように、鋭敏繊細を極めたヘッセも、・七色に輝き踊るガラス玉・や全ての色の光が融合すると無色透明になる現象を目の当たりにしつつ、創作に耽っていた可能性も排除しきれない。
しかしこれ以上の詮索は無意味であろう。ヘッセは研究され学ばれることを嫌うからだ。求めれば対象は姿を隠す。あるがままに見て聞くがよい。ヘッセの精神世界はその魂に触れさえすれば充分なのである。
二五世紀頃のユートピア「カスターリエン」で最高位の「ガラス玉演戯名人」にまで上り詰めた主人公クネヒト(僕/奴隷)は、所詮演戯は作られたモノに過ぎず、その完璧さこそが自由な創造性を奪い時間の超越、永遠や解脱を阻むと思い知ると「カスターリエンの没落」の予感の中、友の息子ティトーに一介の教師・僕クネヒトとして仕えるべく、ユートピアから人間生活の現実と自然世界へ、ティトーの待つ高地の湖畔にある山荘へと向かう。しかしティトーに会った翌朝、湖に飛び込んで対岸へと泳ぐ青年に誘われるように水に入ったクネヒトは、旅の疲れと水の冷たさに湖底に沈んで浮いて来ることはなかった。僕となり犠牲の死を遂げたクネヒトは、しかし十字架のキリストのように、命ある人生を・新しい人・に生まれ変わらせる偉大なマイスター(師/名人)の役割を果たしたのだ。「彼の道は、円形を描いて進んだ。楕円形、あるいはラセン形、…直線系でないことだけは確かだった。直線は明らかに幾何学にだけあるもので、自然や生活にはなかった。」漂泊の魂にとって、人生はいつも回り道であり予測不能である。
ヘッセの住む所、赴く所には川と湖があった。水は命の源であると同時に命を奪いもした。雨は川となり海となって天に昇り自然界を循環していた。水は常に流動的で融通無碍に形を変えて器に収まり、清濁併せ呑んで全てを融合し下流へと運んで行った。風景は変わらなくても水は常に新しかった。
『ヘルマン・ヘッセ エッセイ全集2』はヘッセ理解の助けとなる。とりわけ『魔術師』『略伝』『我がまま』『筏下り』『仕事の夜』『私の信仰』『神学断想』をお薦めしたい。
ヘッセを語る際大切なのは、少年時代「一番なりたかったのは断然魔法使いだった。…物書きの仕事をするようになってから、自分の作品の背後に姿を消し、豊かな意味を持つ遊戯的な名前の背後に隠れ、それで自分を見えなくしようと、何度も試みたのである。」と云う魔術性・遊戯性そしてフモールの世界観ではなかろうか? ドイツ文化のフモールは英語のユーモアを凌駕する深い哲学性を帯びていて、禅の〈空〉に匹敵し〈無の境地〉に近い。
そしてもう一つの特色は〈我がまま〉への憧憬であろう。「私が大いに気に入っている徳が、一つだけある。それは我がままという……我がままな人は、たった一つの無条件に神聖な、自分自身の中の掟、〈我がまま〉なる〈心〉に従うのである」と、自己に正面から向き合い、「本来の自己(真我)」の声に聴くことを説くのもヘッセである。
ヘッセを異端とか仏教改宗者と見るのは当たらない。母方の祖父と父はインドで伝道師だったから、書斎には密教的な神々の像が溢れていて、少年ヘッセが心惹かれたのは間違いないが、マルティン・ブーバーの「我-汝の実存主義神学」に傾倒し、スイス、モンタニョーラで八五歳の生涯を閉じ、ルガーノ湖畔の聖アボンディオ教会墓地に眠るヘッセの信仰を、疑うべきではないと筆者は考える。
板倉素子
いたくら・もとこ=千葉経済大学短期大学部名誉教授 比較文学/異文化コミュニケーション
つづきを 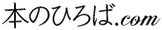 で見る
で見る


