按手礼を受けた牧師であるとはいえ、留学のために休職をしていた期間もあったため、私自身はまだまだ牧会経験の浅い者です。けれども、短いなりのこれまでの牧師としての歩みを振り返る時、どうにかならなかったのかと思うことが一つあります。それは育児休暇の取得です。
1人目の子が産まれた直後は、着任して間もない時期でしたので、育児休暇をお願いすることまではできませんでした。毎週の礼拝とその準備に加えて、祈祷会とナザレン教会の関東地区牧師会内で任された役割があったため、育児や家事の負担を妻にかなりかけてしまった時期でした。もっと家族を大切にするために、勇気をもって断り続ける必要があったと今でも後悔しています。
2人目の子の出産時期が近づいた時、1人目の時の反省を活かして当時牧会をしていた教会役員会と牧師の働き方について相談をしました。もっと振り切った提案をするべきだったのでしょうが、当時の私が提案した内容は、子どもが産まれてから半年間は、私が祈祷会に出席するのは月2回とさせていただくというものでした。当時の教会役員会のみなさんは理解を示してくださり、半年間ではなく「しばらくの間」という形で、もっと柔軟に休みを延長できるように配慮してくださいました。教会総会でも議題として出し、教会全体としても意思決定をしました。しかし、詳細は伏せますが、結果的にはうまくいきませんでした。当事者である若い牧師とその家族は一番立場が弱いため、当事者にとって一番良い形での休暇の取得ができないと思い知りました。
今後、自分たちが年齢を積み重ねていく中で、自分や家族の健康上の理由や親の介護などにより、教会に休暇をお願いする時期がまたやってくるかもしれません。しかし、過去に比べてみれば、牧会者としての経験や人生経験の積み重ね、教会との信頼関係の構築の度合い、そして自分たちの年齢が上がることにより、イレギュラーな休暇を教会に依頼しやすくなってくるでしょう。けれども、育児休暇は経験の積み重ねも少なく、教会との信頼関係もまだまだ構築中の時期に必要となるものです。だからこそ、当事者以外の人たちの手によって、制度的に支えられる必要があるのでしょう。
私が所属しているナザレン教会は、160以上の地域に交わりが広がっている世界教会です。世界教会として、ナザレン教会は『マニュアル』という教会規定を持っています。2023年版の『マニュアル』は、牧者の召命についてのセクションの前半部分において、地域教会が牧師の育児休暇を考慮するように勧めています。その際、理事長が教会と牧師との間に入って、お互いの合意できる方針を定めるようにと促しています。組織的に若い牧師たちを守ることのできる良い制度だと思います。
日本のナザレン教会では運用されていないものですが、コレカラの牧師たちのために必要な時が来たならば、きちんと声を挙げられるように準備しておかなければならないと思わされています。小さな教団ですが、若い牧師たちが育児休暇を必要とするタイミングで、半年間ほどの支援を行う協力体制は教団として作れるはずですから。家族を守るため、牧師には育児休暇が必要です。教会や教団として支援を行うことは悩ましいことなのかもしれませんが、きっと育休制度を真剣に考えて取り入れることは、牧師の家族を守り、結果としてコレカラの教会の交わりを健全に保っていくことにつながると私は信じています。
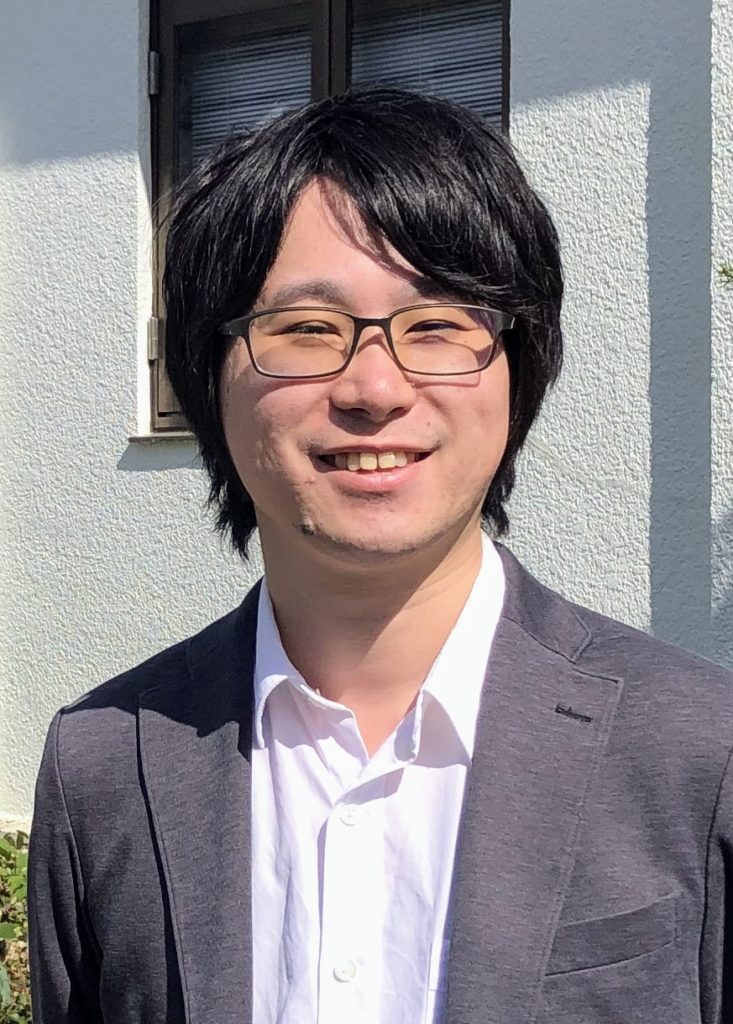
いなば・もとつぐ 1988年茨城県生まれ。日本大学、日本ナザレン神学校卒業後、数年の牧会期間を経て休職し、アジア・パシフィック・ナザレン神学院(フィリピン)とナザレン・セオロジカル・カレッジ(オーストラリア)に留学。修士号取得後、日本ナザレン教団小山教会に着任。趣味は将棋観戦とネット対局。





