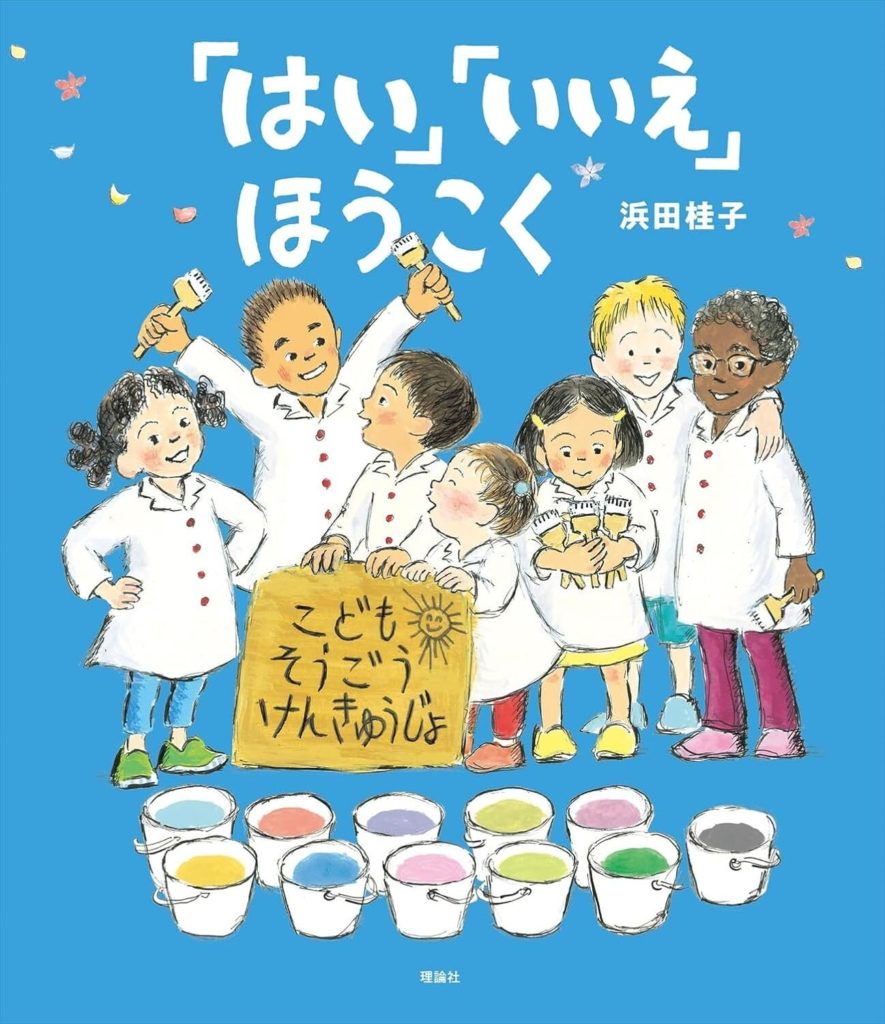横浜YMCAが平和について考える機会として毎年2月11日に開催している「ピースフォーラム」が、今年も湘南とつかYMCA(横浜市戸塚区)の会場とオンラインの併用で開催された。今年は会員事業委員会(古賀健一郎委員長)を中心に企画・運営を行い、「絵本から学ぶ へいわってどんなこと」をテーマに、浜田桂子氏(絵本作家·画家)を講師として招いた。国を超えた意見交換を積み重ね、各国の歴史を踏まえて実現した取り組みや経緯などを聞き、多様な視点から平和について共に学び、考え、平和の意味と大切さを問い直す機会にしたいと企画したもの。
浜田氏は、中国・韓国・日本の絵本作家と平和絵本シリーズを企画し、2011年に『へいわってどんなこと?』を3カ国で共同出版(日本は童心社)。累計発行部数は13万部を超え、香港版は「2020 Hong Kong Book Prize」を受賞した。
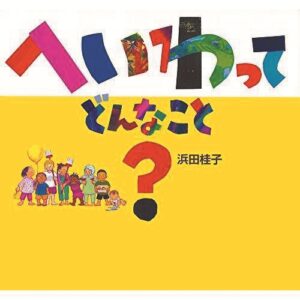
講演で浜田氏は、2005年から2006年にかけて、日本の絵本作家である田畑精一、田島征三、和歌山静子の3氏とともに、中国、韓国の絵本作家に平和絵本作りを呼びかけた「日・中・韓平和絵本プロジェクト」の概要を説明。過去の日本による武力侵略や植民地支配の歴史を直視した上で、連帯して平和絵本を作る意味は大きいと考えての提案だった。
呼びかけに応じた中国、韓国の作家らとともに絵本を作り上げる過程を、当時の写真を交えながら紹介し、「加害と被害、双方の痛みを共有する努力を重ね、意見を述べ合いながら絵本を作るという、前代未聞の冒険だった」と振り返った。
試作段階の『へいわってどんなこと?』をめぐっては、「せんそうのひこうきが とんでこないこと」「ばくだんが ふってこないこと」「いえやまちが はかいされないこと」との記述について、韓国の作家から「受けた被害だけで戦争をとらえ、与えた被害の認識が薄い」との指摘を受けたという。その後、ナレーターである子どもを主体的で能動的な存在に変更し、「せんそうを しない」「ばくだんなんか おとさない」「いえやまちを はかいしない」との表現に修正された。
さらに、「だれもひとりぼっちにしない」という文案に対して田畑氏から「ひとりぼっちはとても大事なこと」との指摘を受けた浜田氏は、自身にはない発想だったと気づかされたと回顧。「戦争はひとりぼっちを許してくれず、個人の行動を認めなくなる。やがて排除し、非国民のレッテルを貼る。個人の意見、個人の立ち位置は、絶対に尊重されなくてはならない」と思い至り、この文言は削除された。
日・中・韓平和絵本プロジェクトは、その過程そのものが「平和をつくる」作業だった。完成した11冊を携え、現在も国内外で子どもたちと「いのちと平和を考えるワークショップ」を行う浜田氏。2020年に香港で開かれた読書会では、当時の情勢と相まって「いやなことは いやだって ひとりでも いけんが いえる」のページが共感を得た。韓国では、『へいわってどんなこと?』を入学式で読む先生もいる。ロシアによる侵攻後に出会ったウクライナの学生からは、「子どもたちに希望を与えることができる、とても大切な本」との感想も寄せられた。
ある時、国内の学校で「今まで生まれてきてよかったと思ったことは一度もなかったけれど、『へいわって ぼくが うまれて よかったって いうこと』という文を読んで、初めて生まれてきてよかったかもしれない思った」と打ち明ける子どもと出会う。貧しい地域もたびたび訪れてきたが、こうした反応は日本特有で、「おもいっきり あそべる」「あさまで ぐっすり ねむれる」というページで首を振る高学年の児童がいることも気がかりだと話す。
そうした子どもたちのつぶやきを絵本にしたのが、『「はい」「いいえ」ほうこく』(理論社)。浜田氏は講演を、「自分を大切に思える力は平和をつくる支柱。戦争が起きている今だからこそ『人間は、信頼し共感しあえる』と希望を伝えたい。そのために子どもの本は、存在する」と結んだ。