思春期に入ると、子どもたちは罪についてスピリチュアリティーに気づくようになる。神が地獄の火という罰を示し「やってはいけない」ということで、禁じられていることがある ―― 罪とはただそれだけのことではない。子どもたちは徐々に(あるいは突然に!)「神のようになって自立してみてはどうか」という要請こそが罪の正体だと気づく。「善と悪を知ることで、神のようになる者となる」(創世記3章5節)という声が罪である。その声は生理的な満足を約束する(その木は食べるによく……目に麗しく見え)。それだけではなく、霊的な深化をも一気に成長させて「超越」を渇望するようになる時まで、子どもたちはそのような誘惑に晒(さら)されることはない。幼いうちは、生活が保護されているために誰かに大きく依存し生きているのだから、子どもたちは「自立」しようとする思いは決して沸いてこない。しかし、思春期や、思春期が近くなると、「子どもだから」との抑制を放棄し、大人になりたいと思いイライラするようになる。そこに「神のようになれるよ」と、悪魔が安直に約束してくる。その結果「あなたのために」と定められた禁止事項にもう納得いかなくなり、自分たちの正当な権利を侵害してスピリチュアルなものへのアクセスを邪魔する束縛と考えてしまう。そして、それを束縛であると思い、腹が立つようになる。
思春期のひらめきのようなものが全く正しいものとされる場所が一つある。それが「罪」である。それは極めて霊的なものだ。罪には道徳的な次元がある。もちろん、人々を危険にさせたり、あるいは人々に生きていくうえで困難にさせる行動の問題もある。それは当然なこと。罪は行為の問題なのだ。罪によって人は危険に近づく。そうした時、あるいは別の場合でも、人は罪によって他人と共に生きていくのが難しくなって行く。罪は霊的な問題であり続ける。意味・目的・意義の探究という問題がそこにはある。子どもにとって罪とは道徳的問題として存在する。思春期になると、罪の霊的次元が浮上してくる。「神のようでありたい」と熱望した最初の罪は「霊的な企て」として、まず存在していたのだ。例えば「自分たちよりも立派な何者かになろう」とか「もっとよい人になろう」という企てとして、罪は顕在化する。あるいは「死ぬ存在にすぎない」わたしたちの平凡でつまらない性質を、一瞬でも超える経験をするという企てとして罪は顕在化するのだ。
もし、わたしたちには罪などない、と言い張るならば、その時わたしたちは、神と矛盾しているのだ。神を嘘つきと言っているのだ。それはつまり「わたしたちは神について何も知らない」ということをただ露呈しているだけなのだ。
―― ヨハネの手紙(一)1章10節
*引用される「聖書の言葉」はピーターソンさんの翻訳・翻案を訳したものです。

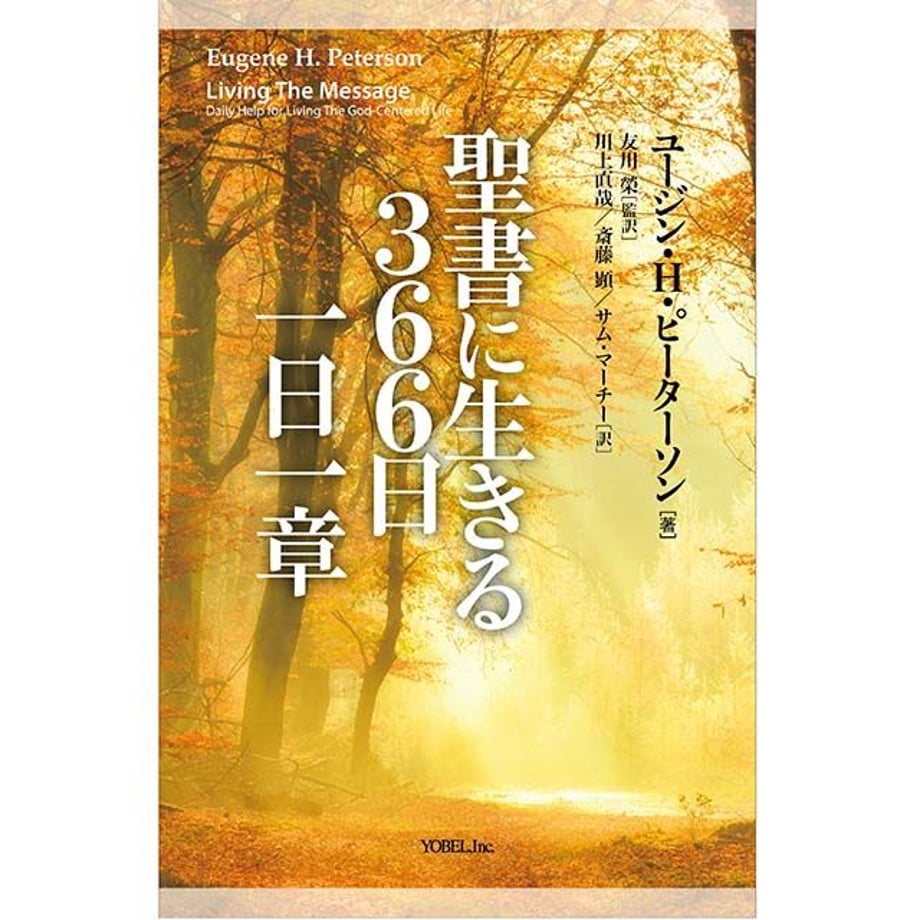 出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)
出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)