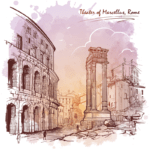懐疑主義と、アウグスティヌスの哲学との関係
29歳の青年アウグスティヌスは、おそらくはキケロの『アカデミカ』を読むことを通して、懐疑主義の思想に共感を覚えるようになってゆきます。
「それというのも、アカデミア派とよばれる哲学者たちのほうが他の哲学者たちよりも賢明であったという考えがまたわたしに起こったからである。かれらはどんなことについても疑わねばならぬと考えて、どんな真理も人間によってはとらえられることはできないと考えていた。すなわち、わたしは、かれらの真意をまだ理解していなかったけれども、かれらは、一般に信じられているように、それが明らかにほんとに彼らの説であったと考えていたわけである……。」
『告白』の叙述においては、これ以上のことは触れられてはいませんが、この出来事は、その後のアウグスティヌスの歩みを考える時には非常に大きな意味を持ってくることになります。今回の記事では、このあたりの事情について見てみることにします。
「疑う人間」から「信じる人間」へ
まずは、大きな流れを確認しておくことにします。32歳の時に「取って読め」の出来事によって決定的な回心を経た後のアウグスティヌスは、29歳の時には共感を覚えていたアカデメイア派の懐疑主義の思想に対して、内面において、徹底的な戦いを繰り広げることになります。
キリスト教の信仰を持つ前のアウグスティヌスにとっては、「人間には、いかなる真理も知ることはできない」という主張は理のあるものに見えました。さまざまな主張をそのまま受け入れることなく、厳しく吟味するという懐疑主義の姿勢から多くを学んだことも、紛れもない事実です。
しかしながら、32歳でキリスト教への回心を経験した後の彼が最初に取り組んだ試みの一つとは、この懐疑主義の主張を掘り崩すことでした。具体的には『アカデメイア派駁論』を始めとするテクストを書くことのうちで、彼はその後に「アウグスティヌスの哲学」(これはいわば、はるか後に哲学の歴史において「超越論哲学」として知られることになるものの方向性を素描するものに他なりませんでした)として知られることになるものの土台を少しずつ作り上げてゆきます。
すなわち、「取って読め=決定的な回心の出来事」を通して、アウグスティヌスは「疑う人間」から「信じる人間」へ、確かなことは、何一つ確かなものがないということだと考える人間から、揺らぐことのない確かさに触れたと信じる人間へと変えられたのです。今回の記事では、『告白』のよく知られた一節を引きつつ、この「揺らぐことのない確かさ」なるもののあり方について考えてみることにします。
「わたしはあなたを疑惑をもってではなく、確信をもって……」
『告白』第十巻第六章において、アウグスティヌスは次のように言っています。
アウグスティヌスの言葉:
「主よ、わたしはあなたを疑惑をもってではなく、確信をもって愛するのである。あなたはわたしの心をあなたの御言をもって貫かれたから、わたしはあなたを愛した。」
同じような表現はこの本の中で何度も繰り返されていますが、「決定的な回心の出来事によって、神の愛のうちに入れられた」ということの確かさはアウグスティヌスにとって、ある意味では、「わたしが存在する」ということの確かさよりも深いと言わざるをえないような確信を与えるものでした。すなわち、「生きている神からの働きかけによって、信じることのうちへと投げ込まれた」ということの確信はあらゆる理屈づけを超えて、彼の実存そのものを、生き方そのものを根底から変えずにはおかないような、そうした確信に他ならなかったといえます。
もちろん、アウグスティヌスは哲学者でもあるので、『アカデメイア派駁論』をはじめとするさまざまなテクストでは、さまざまな論拠を一つ一つ打ち立てながら懐疑主義と対決するという作業を行ってもいます。しかし、アウグスティヌスという思索者の根底にあるものを、彼を突き動かしていた実感と共に理解するためには、そうした論理の次元における格闘よりも、まずもって、上に語られている「確信=確かさ」の内実を掴みとっておく必要があるのではないか。
すなわち、人間には「わたしは自分が知っていると思っていることを、本当に知っているのか?」と疑うことも確かにできるけれども、人生には、そうした疑惑や懐疑を超えて「信じる人間」へと変えられざるをえないような、そうした〈根底的転回〉の出来事も起こりうるのではないだろうか。アウグスティヌスにとって、32歳の時に起こった「回心=取って読め」の出来事は、自らの存在の奥底において「神の愛」の確かさに刺し貫かれるような、そうした決定的な出来事にほかなりませんでした。この出来事は彼にとって、疑うこと、懐疑することがもはや意味を持たなくなってしまうような、ある種の「実存の全面的な変容」を意味するものであったと言うこともできるかもしれません。『告白』を読解する試みにとって、「回心=取って読め」の出来事こそが、他のすべてのことがその周りを回ることになる中心点となって迫ってくるゆえんです。
おわりに
「古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。」こうして見てくると、回心という出来事それ自体が、あらゆる疑いを打ち破らずにはおかないような「『実存の真理』における〈転回〉」にほかならないという事情が、少しずつ浮かび上がってきます。ここには「信じること」という『告白』の主要テーマが深く関わってきているので、次回の記事では、その点について掘り下げてみることにしたいと思います。
[ありがとうございました。これ以降の『告白』読解では、「回心とは何か?」という問題に焦点を当てつつ、アウグスティヌスがたどった生涯について考えてゆくことにします。読んでくださっている方の一週間が、平和で穏やかなものであらんことを……!]