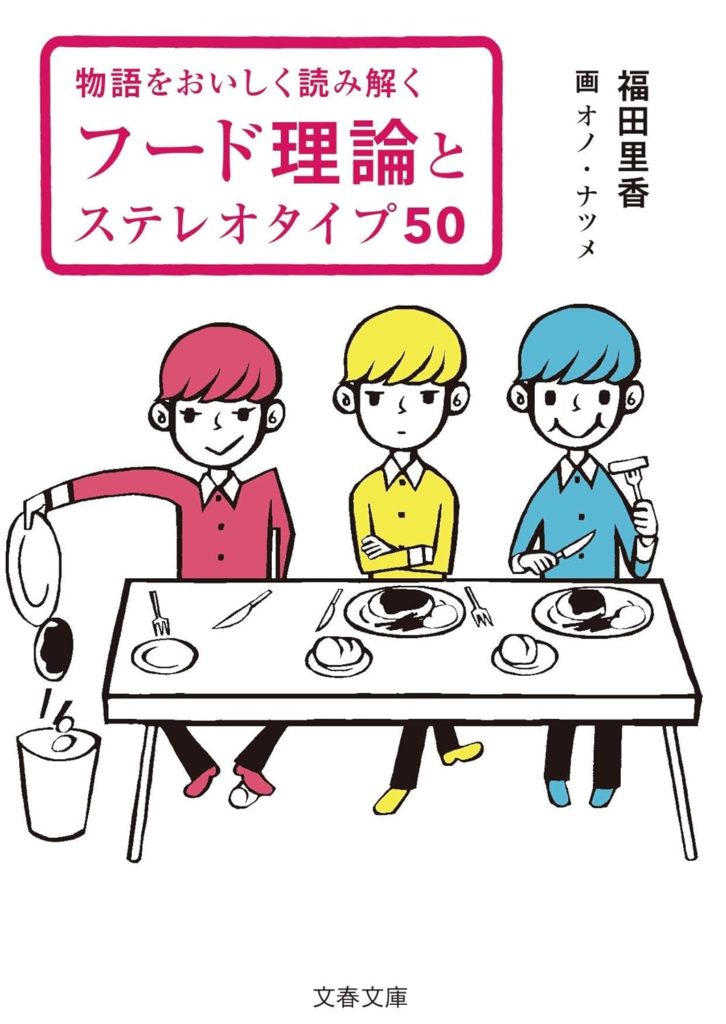「同じ釜の飯を食った仲間」という言い回しがある。苦楽を共にした親しい間柄を指す慣用句だが、食事と人間関係が深く結びついていることが分かる表現でもある。食を通じて物語を読み解く「フード理論」を提唱した福田里香は、著書『フード理論とステレオタイプ50』の中で、「正体不明者は、フードを食べない」という原則を指摘する。皆で食事をするシーンで一人だけ何も食べない人間がいれば、その人物は怪しく見える。腹の底が分からないからだ。逆に言えば、食事は相手に腹の底を見せる行為でもあるということになる。確かに初対面の相手と親しくなろうとする時、ただ向き合って話すよりも、飲食を介した方がスムーズにいくことが多いように感じる。
誰かと一緒に食事をする「共食」は、宗教と深く関わってきた。日本社会では直会(なおらい)があげられるし、キリスト教でも聖餐や愛餐がある。いずれも親睦を深め、信者同士の結束を強化する機能があるといえる。私が調査している在日コリアン教会もまた、共食を重視している。在日コリアン教会では、たいてい食事スペースやキッチンが当たり前のように設けられている。そのため原則毎週、礼拝後は昼食を皆でとる習慣がある。
提供される食事は、基本的に韓国料理である。そのため、渡日してきた1世にとっては「祖国(故郷)の味」を懐かしむものとして、日本生まれの2世以降にとっては自らのルーツを確認するものとしても機能してきた。仲のいいグループ同士で食事をとりつつ、祖国(故郷)の話に花が咲くこともあれば、韓国料理に不慣れな日本人などに食べ方指南を始めるグループもいる。礼拝前は黙祷するなどし、私語は慎むべきものとして注意されることもあるため、礼拝後の食事の時間が貴重な交わりの場になるのだ。ちなみに、教会によっては子ども食堂を行っているところもあり、食を媒介とした教会と地域社会の交流も見られる。
ただし、共食はポジティブな文脈でのみ語られるものでもない。例えば、教会での食事作りは多くの場合、女性の役割という規範が存在している。彼女たち(特に近年韓国から渡ってきた1世たち)は教会活動に熱心で、奉仕も積極的に引き受ける傾向にある。教会は彼女たちの「献身」や「奉仕」に依存することで、共食を可能にしているといえる。
また共食は、集団の一体化を強化する一方で、アレルギーや会食恐怖症など、何かしらの理由で参加しない/できない人々の排除にもつながりうる。共食を前提とするような宗教組織や儀礼の場合、そうした人々の「仲間入り」を阻害するような選別が、無意識のうちに行われてはいないだろうか。あるいは逆に、戒律によって食が制限されている宗教者もまた、日本社会の共食の場で想定されていないことは多いだろう。
コロナ禍を経て、共食の意義が再び強調されているように思う。行政は「孤食」を避けるべきものとして扱う一方で、共食をポジティブに評価し、積極的に推奨している。子ども食堂もその文脈で意義づけられることがある。確かに共食は楽しく有意義な場だ。しかしその一方で、ジェンダーなど特定の属性を持つ人々に過度な負担を強いる構造になっていないか、あるいは特定の属性を持つ人々が選別/排除されていないかなど、共食という場に内在する権力構造や選別/排除のシステムにも目を向けなければならない。

荻 翔一(宗教情報リサーチセンター研究員)
おぎ・しょういち 1989年千葉県生まれ。東洋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。日本学術振興会特別研究員(PD)。共著書に「高齢化問題に取り組む韓国系キリスト教会――大阪市・在日コリアン集住地域を事例に」高橋典史・白波瀬達也・星野壮編『現代日本の宗教と多文化共生――移民と地域社会の関係性を探る』(明石書店)。