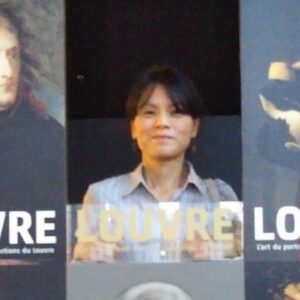戦後80年。4人の一兵卒の日記を紐解きながら、歴史の真実に迫るドキュメンタリー映画「豹変と沈黙ーー日記でたどる沖縄戦への道」が8月16日から劇場公開される。監督は、前作「夜明け前のうたーー消された沖縄の障害者」で1972年まで沖縄社会に存在した「私宅監置」の実態を描き、文化庁映画賞を受賞したフリーランスのテレビディレクター原義和氏。「夜明け前のうた」をきっかけに映画の世界に大きな魅力を感じ、これまで大事なテーマとしてきた沖縄戦を取り上げ2本目となる映画を制作した。戦場体験者の多くが世を去った現在、沖縄戦から日中戦争まで遡(さかのぼ)るという新たな視座で、戦中日記を手がかりに失われつつある記憶を呼び起こすことに挑戦した原監督に話を聞いた。
────まず、原監督の信仰についてお聞きしてもいいでしょうか。
私の父は日本基督教団の牧師で、私が子どもの頃、名古屋にある金城学院高等学校の宗教主事をしていて、毎週日曜日には名古屋北教会(名古屋市北区)に一緒に通っていました。食前の祈りは日常で、聖書も身近なものとして常にあり、キリスト教は物心ついた時から私の心身に染み込んでいます。東京に出てきてからは、豊島区にある巣鴨ときわ教会に所属し、その頃、牧師の平良愛香さんとも出会い、友人として今回の映画でも劇場での舞台あいさつなど協力していただいています。約20年前に沖縄に移住してからは定まった教会はないのですが、自分のバックボーンにキリスト教があることは確かです。
────信仰は作品に影響を及ぼしますか。
前作の「夜明け前のうた」は単なる差別偏見を訴えたものではなく、社会制度として障害者を何年も隔離するという私宅監置の実態を明らかにしたもので、闇の中に置き去りにされたというか、見棄てられた人びとに焦点を当てた映画です。偉そうに私が言える立場ではありませんが、キリスト教の精神は社会の最底辺で蹂躙(じゅうりん)されている、例えばハンセン病患者や障害者など弱くされた人びとと出会うことではないか、イエスはそのような人びとの人間性を回復させる存在であったと受けとめています。私が目指す表現者の在り方が、キリスト教信仰に基づいているなどとカッコよく言うつもりはありませんが、両親の影響で育まれてきたイエスを救い主とする信仰は、前作の「夜明け前のうた」には色濃く反映されていると思います。
────今回の作品では戦争をテーマとされていますが。
テレビディレクターとして、障害者福祉や沖縄戦、東日本大震災後の福島などをテーマに番組を作ってきました。これらは自分のライフワークとも思っていて、「敗戦80年」という節目も意識し、「夜明け前のうた」の次は沖縄戦をテーマに映画を作ろうと決めていました。

Ⓒ Yoshikazu Hara 2025
────4人の一兵卒の日記をたどりながら、何を伝えたいと思われたのでしょうか。
敗戦から80年、戦争体験者から直接話を聞くことが難しくなっている今、どういう形なら新作が撮れるのか、一次資料として残っている『日記』はその大きな手がかりになると考えました。もちろん、それが絶対ではなく、映画に出てくる日記は全て、取材の中でたまたま出会ったものでしかなく、また一兵卒が書いたものです。大きな戦略や戦術などはよく分からない中、上官に言われるままに動きまわり、“虫の目”のように見えた範囲のことだけが記されています。それで戦争の全てが分かるわけではありませんが、その中にも戦争の真実はあるだろうと信じて映画を作りました。
────4人の日記には接点のようなものがあったのでしょうか。
書かれた時期は3人は重なっていますが1人は数年遅れています。4人とも出身地が違いますから、部隊もバラバラです。1人は沖縄の金城信隆さんという方で、大学の学生寮で書いた日記で、あとは戦場で合間をみて書いた個人の陣中日記です。日記とは別に、軍の部隊が書く「陣中日誌」というものがあります。これは個人の日記と違って軍の公式記録なので、命令内容や移動経路、戦闘状況などが記されますが、そこにはあまり生の感情は出てこない。一方、個人の日記は「戦争は嫌だ」などと、かなり感情的なこともはっきり書かれており、一兵卒の心の動きがよく分かります。そういう意味で日記に戦争の真実は含まれていると思いますが、4人それぞれの心の動きを一つの物語にするという点で大きな挑戦でした。

Ⓒ Yoshikazu Hara 2025
────記録だけでも、感情を記したものでも真実は語りきれないということでしょうか。
日記には、本人が戦場で見た全てが書かれているわけではありませんし、あえて書かなかったこともある。だから、タイトルに「沈黙」という言葉をあえて入れて、書かれていないことにも、実は大事なものが隠れているのではないかと問いかけています。本人たちに、戦場体験は『隠しておきたい』という気持ちがあることは間違いありません。映画に出てくる息子たちは、生前父親から戦地の話(それが全てでないにせよ)を聞いているので、その話から日記に書かれていないことも、なんとなく想像できる。特に熊本に住む田中信幸さんは、父親から戦時中の日記を譲り受け、それを丁寧に読み解き、分析したという経験を持っています。しかし、取材で出会った多くの家族は、父親と戦争についてほとんど話をしていません。たとえ日記を譲り受けたとしても目を通すのは稀です。映画に出てくる昇さんの日記がそうであったように、中にはそれを古物商に流してしまうケースもあるのです。

Ⓒ Yoshikazu Hara 2025
────そういうことを聞くと、田中さんとの出会いは貴重でしたね。
彼が学生運動をしていた1970年代からのことですが、父親に対し「あなたが参加した戦争は侵略戦争だったのではないか」と真正面から問うたということに驚かされました。尊敬せずにはいられません。また、それに応えようとした父親の姿にも心打たれます。多くの人が、そのように父と戦争をめぐって向かい合うことはできず、父のほうも語ったとしても当たり障りのないことや、このくらいだったらいいかなと思ったことだけを語ってそのまま亡くなっている。戦後の日本社会では、そうした語られなかったことが数限りなくあり、それこそが重要ではないか、我々は大切なことが欠落した社会で生活しているのではないか、ということを考えたい。そこは大事にしたかった点です。
────映画では日中戦争と沖縄戦のつながりを示していますが。
1945年の沖縄戦の背景に日中戦争があると、以前から考えてきました。戦争は突然始まるわけではなく、前史があるわけで、その一つの起点として日中戦争がある。沖縄戦時の軍司令官と参謀長は、中国戦線での武勲をおそらく胸に持って沖縄に乗り込んでいますし、主力部隊は中国からの転戦でした。沖縄にやってきた日本軍は、強かんや略奪など暴虐の限りを尽くした中国戦線の雰囲気そのままで、軍紀の乱れも問題になっていました。両者は間違いなく地続きです。そのような両者の関係を考えた時、沖縄の金城信隆さんの日記は、複雑な思いを抱きながら読まざるを得ませんでした。

Ⓒ Yoshikazu Hara 2025
かつて沖縄は、琉球国として独立した国で、中国とは友好関係を濃厚に築いていました。それが1879年に日本に併合され、アジア太平洋戦争でも沖縄の若者は「日本兵」として徴集され中国大陸に攻め入ることになりました。金城さんは上海のエリート校「東亜同文書院大学」に進学し、日中提携という学校の理念の通り、彼も日中の架け橋になりたいと考えたはずですが、日中戦争は泥沼化し、彼も戦場に駆り出されていくわけです。沖縄の人びとは、かつての友好国の人びとを日本兵として殺戮させられるという歴史の屈折体験があります。沖縄戦というと沖縄で何が起きたかということはよく語られますが、日本兵にさせられた沖縄の人びとがアジアで何を強いられていたのかということにも目を向ける必要があると思います。
────金城さんが戦地で「豹変」していく姿には、他の3人とは違う体験があったかもしれないということですね。
ただ、中国の側からすると、どちらも自分たちを攻撃する同じ日本兵なんですね。映画には、日本兵に目の前で一家を惨殺された中国人被害者の2世(娘さん)が出てきますが、私はあの証言を大切に考えています。あの人が語った中国の人びとの凄まじいトラウマ。元日本兵も、戦場での過酷な体験に基づくトラウマにその後、悩まされたことを考えれば、彼らも戦争の被害者と言えます。しかし第一に、日本兵は戦場における加害者であり、実際にとてつもない被害に遭った人たちが大勢いることに目を向けなければならない。この中国人女性は「父親は一生、笑顔のない人だった」と話しました。日本兵に家族を惨殺されたトラウマで笑顔を失った父親の苦しみ。父親の笑顔を知らずに生きることを強いられた彼女の苦しみを想像してみる必要があります。日本軍はとんでもない過ちを犯してしまいました。ですから、元日本兵も大変だったと振り返るだけで終わらせては絶対にならないと思い、あの場面を無理矢理入れました。

Ⓒ Yoshikazu Hara 2025
────加害国としての責任はどう果たすことができると考えますか。
特に8月は、広島・長崎の原爆投下、ポツダム宣言受諾、天皇の玉音放送などがあって平和について考えるいわば“平和月間”となっています。被害体験を振り返り、大切な人を失ったつらさを伝えていく。もちろんそれも大切ですが、日本が加害者としてアジアでどんなことをしてきたか、繰り返し学ばないといけないと思います。先日、映画の特別上映会を開き、中国人やモンゴル人の若者と日本人大学生が意見を交わし合う時間を持ったのですが、参加した学生は皆、非常に意識が高かったのですが、話に出たのは、日本の教育では近代史が軽視されていて、この100年どのように歩んできたか、教育の機会が少ないということでした。逆に中国では「愛国教育」も含めて、近代史をかなり濃密に学びます。太平洋戦争が日中戦争の結果としてもたらされたことや、その日中戦争で日本がどれだけ残虐なことを行ない、国際社会からどういう批判を受けたか、それらを学ばないとアジア太平洋戦争をよく理解することは難しいはずです。戦争の何を語り継いでいくべきか、沈黙の中にも耳を傾け、歴史の真実を繰り返し学び、想像するひとりでありたいと思います。
8月16日から29日まで、東京・新宿K’s cinema(ケイズシネマ)で公開。
※全国順次公開
大阪・第七藝術劇場で上映決定