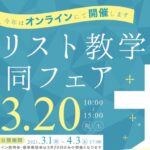創立75周年を迎えた玉川聖学院(安藤理恵子学院長)は9月27日、同学院(東京都世田谷区)で平和講演会を開催し、講師に招かれたアンダーソン大学前学長のジョン・ピストル氏が「Civil Discourse in an Uncivil World――混迷の時代に平和を語る」と題して講演した。
米国神の教会の会員でもあるピストル氏は、米連邦捜査局(FBI)副長官として、テロ対策や危機管理の最前線で活動。2010年にはオバマ大統領によって、運輸保安庁(TSA)長官に指名され、米国上院にて全会一致の承認を受けた。米インディアナ州のアンダーソン大学は、歴代理事長の母校でもある。今回、前日に行われた記念式典にも出席した。
1950年、日本神の教会連盟初代理事長の谷口茂寿氏によって創設された同学院は、今日まで1万2500人の卒業生を輩出し、現在も中等部・高等部6学年で約800人が在籍している。
講演でピストル氏は、自身の経験と信仰に基づいて現代の分断は意見の違いそのものではなく、対話の方法が損なわれていることに起因すると指摘。人はしばしば、相手を「意見」そのものと同一視し、人格を否定する言葉へと容易に傾くため、それが社会の歪みを深めていると説いた。
また、自身が家庭や教育現場で経験した対話の学びを紹介した。対話とは、話すことと同じだけ「聞くこと」を含んでおり、勝ち負けではなく、相手を理解しようとする意志こそが真の対話の基礎になる。礼節ある対話には「語り方(トーン)」と「内容」の二つが重要であり、声高に主張することが力なのではなく、「静かに、しかし確かな信念をもって語ること」が説得の力を生むとした。
インターネット上のコミュニケーションが対話を困難にしている現状にも言及。匿名性が高まると、人は自らの言葉に責任を持たなくなり、攻撃性が増す。結果として、考えの違いは容易に敵意へと転化される。「人とその意見を区別して受け止める勇気が必要」と述べた上で、人格の尊厳を守ることが対話の出発点であると強調した。
歴史的な事例として、ベルリンの壁の崩壊、ソビエト連邦の解体、天安門広場での抗議活動などを挙げ、平和的な対話と暴力的な対立の違いを説明。イエス・キリストやキング牧師の言葉などを例に、平和をつくる営みは受動的な沈黙ではなく能動的で関係性に根ざした行動であるとし、「勝つためではなく、つながるために語り、理解するために聴こう」と呼び掛け、その姿勢こそが、分断の時代における私たちの責務であると述べた。
最後に、「私たちは相手をコントロールすることはできないが、自分自身をコントロールすることはできる」とし、46年間の結婚生活で妻を変えようとするのではなく、まず耳を傾けて共に成長してきたと述べ、平和的な対話は沈黙のためではなく、変革のための最も強力なツールであり、その変革は今日から始めるべきだと結論づけた。
終了後、約1時間にわたる質疑応答では、参加した在校生や卒業生から多岐にわたる質問が投げかけられた。
講演内では、保守派の活動家チャーリー・カーク氏が銃撃された事件にも触れ、追悼式で「犯人を許す」と宣言した家族の言葉も紹介したピストル氏だが、アメリカの現状について問われると、「今まさに転換期を迎えており、前向きな変化を起こすチャンス」との見解を示し、「トランプ政権下でアメリカの民主主義が危機に直面しているのではないか」との質問には、アメリカの政治システムが大きなストレス下にあり、大統領が行政権の限界を試していることを認めた。さらに、「歴史を振り返れば一部の大統領の決定は合法的だったものの、そうでないものもある」とし、他方、ワシントンDCでは連邦検察官ですら特定の事件で大陪審から起訴状を得られない場合もあると解説した。
「リーダーに最も大切な資質は何か」との問いには、リーダーは他者に仕えることを第一に考える「奉仕するリーダー」であるべきだと強調し、若い時は自己中心的だったが、人生を変える経験を経て神を人生の中心に据えるようになった自身の歩みも振り返った。
「攻撃的で理不尽な要求をしてくる相手に対しての対処法」については、攻撃には攻撃で応じるのではなく、「柔軟な答え」で対応することを提案し、そうすることで事態の悪化を防げると述べた。攻撃的な行動は多くの場合、人が他者に対して権力を確立しようとすることから生じると指摘した上で、無礼な態度に対しては親切に対応するという自身の実践を共有し、相手が思いやりのない態度をとった時には静かに「主イエス・キリストの平和があなたとともにありますように」と言うようにしていると紹介した。
同学院は75周年を機に、「社会不安の中にある生徒たちのために、経済的格差なく学びの機会を得られるように新たな奨学金制度を創設」し、記念募金を呼び掛けている。問い合わせは同学院事務室(☎03-3702-4141)まで。