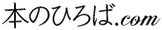「キリスト教と食」というテーマを挙げると、ヨーロッパの修道院が生み出したワインやチーズ、パンなどに関する話かと思われるかもしれない。これはこれで奥の深い世界だが、食は生きることに、従ってシリアスな世界の課題に直結している。今回はこちらに焦点を当ててみたい。
聖書を紐解けば、人間は食べることによって最初の罪を犯し(創世記三章)、キリストのからだに与ることによって罪赦され、神の国の食卓に招かれつくり変えられていくことが語られる。その意味で、食はキリスト教信仰にとって本質的な課題である。
同時に現代に生きる私たちにとって、食は抜き差しならない課題でもある。国連人間居住計画によれば、二〇〇八年に都市生活者が世界人口の過半数を超えたという。つまり、世界の二人に一人は食べ物を自分では作らない消費者として生き、もう一人は飢えたまま誰かの食べ物を作っている。この不正義の構造はそれほど長く持たないだろう。
従って、キリスト教にとって食は重要課題である。この考察を深めるため、以下の三冊をお勧めしたい。
ポール・ロバーツ『食の終焉─グローバル経済がもたらしたもう一つの危機』
『食の終焉─グローバル経済がもたらしたもう一つの危機』
・ポール・ロバーツ:著
・神保哲生:訳、解説
・ダイヤモンド社
・2012年刊
・四六判544頁
・3,080円(電子書籍あり)
本書はグローバルな食システムの問題を指摘する良書である。一言もキリスト教には触れないが、良質なジャーナリズムは常に預言者的であり、神学的な啓発力を持つ。
ロバーツは、本書において食べ物の生産、加工、流通、消費、廃棄に渡る高度に分業化された社会システムのネットワークを「食システム」と名付け、これが人を飢えと重労働から解放し、有り余る豊かさを実現したことを指摘する。その意味では現代の食システムは人類の成功物語である。
けれどもその市場原理に基づいたシステム構築がうまくいきすぎたことが皮肉にもこの食システム破綻の原因である。ロバーツはその事例を次々に示す。
生態を無視した家畜家禽の飼育や食肉加工の大規模集約化によってO─157やサルモネラ菌による食肉汚染が避けられないこと、鳥インフルエンザなど未知のウイルスがアジアの独裁政権に隠蔽されることでパンデミックをもたらすことなど、バイオセーフティーの破綻が示される。化学肥料や農薬による土壌の疲弊は生産能力の低下を引き起こしていること、食経済のグローバル化によってある日突然食の安全保障が脅かされること、また食生活や食文化の荒廃を招き、肥満、糖尿病、アレルギー、心疾患など生活習慣病が避けがたくなっていること、食糧の大量生産にもかかわらず飢餓のリスクは年々高まっていることなど、読者は不快な現実を突きつけられる。しかもこれらはシステムの不調ではなく、成功によってもたらされたことが深刻である。
本書が示す事例はどれもどこかで見聞きしたものが多い。本書の魅力は、ロバーツが「元凶」の糾弾に終始しない点にある。しばしば元凶の如く非難されるアグリビジネスも、彼の視点では巨大食品メーカーの苛烈な要求にあえぐ一プレーヤーに過ぎない。その巨大食品メーカーもメガ・スーパーマーケットやファスト・フードチェーンに踊らされる存在である。巨悪に見えた存在が「自らが置かれた状況の中でもがき苦しむ哀れな存在」であり、「もう一段格上のヒールによって操られているだけの」小物であることを彼は明らかにする。そしてこの食システムの頂点にいる「究極の極悪人」はなんと、一円でも安く買おうとする消費者の私たちなのである。悪人捜しに喜々としていた私たちが、ここで自らに向き合う羽目になるのだ。ささやかなエゴイズムの連鎖が世界を滅ぼす巨悪となることは神学的には原罪論の範疇にあり、本書は食の問題を通じて現代的な原罪の意味を私たちに問いかける。食べものを私的財とはせずに、空気や水と同様公共財として扱う可能性を示唆するのも、経済学的解決を超えてキリスト者に対する啓発力を感じさせる。
D・モントゴメリー、A・ビクレー『土と内臓─微生物が作る世界』
神学や人文系の「古典」に慣れ親しんでいると、日進月歩の自然科学が見ている世界を知らずに過ごすことが少なくない。しかし、自然科学によって人間理解がすでに大きく変わっているならば、それを無視してよいのだろうか。本書は私たちの人間理解をアップデートするよい機会を提供してくれる。新しい人間理解の鍵となるのはマイクロバイオーム(微生物相)である。
近年の生物学では人間をヒト構成要素と微生物構成要素からなる複合的存在として理解するようになっている。人間の体細胞は約三七兆個あるが、それだけで完結して単独の生命活動をおこなっているのではなく、その三〜一〇倍のゲノム量の微生物と相互に影響しながら生きていることが分かってきたからである。つまり、一人当たりヒト三〜一〇人分の目に見えない「隣人」と共生している。この「隣人」の多くは腸内に存在し、ヒトが食べたものを分解して栄養を取ると同時に病原菌からヒトを守る働きなどをおこなう。一人で食べていても実はこの目に見えない隣人たちとの食卓共同体として「わたし」は生きている。人間のいのちの営みは思いのほか共同的である。
しかも人間のゲノムは九九%同じで個人差はわずかであるのに対し、マイクロバイオームは個人差が大きく、同居家族であっても同じではない。人間の精神活動にも影響を与える微生物たちは個性の形成にも大きな影響を与えているようだ。むしろ「隣人」が個性を決定しているかのようである。
他にも「シンビオジェネシス」と呼ばれる、別個の微生物同士が合体する共生関係によってより複雑な生物が誕生した進化のプロセスが示されると、個どころか「種」の概念自体が揺らいでくる。生物学では常識となったこれらの事柄は、ダーウィンに匹敵するインパクトを神学や哲学の人間理解に与えつつある。
モントゴメリーによると、興味深いことに腸内マイクロバイオームと植物の根圏での微生物の働きは対応しているという。腸内細菌も土壌細菌も多くが腐生菌の系統にあり、多糖類を必要とする点で大腸と根は同じ働きをしている。つまり、形態的にはヒトと植物はまるで似ていないが、微生物に注目すると、植物が大地に根を張る存在なのに対し、ヒトは大地を腸内に持ち歩いている存在だと言い換えることができる。土壌の健康とヒトの健康は微生物を介して大地の産物を食べることでつながっているのだ。「大地に根ざした生き方」とはノスタルジアではなく、人間が生きる上での必要条件であり、事実上都市生活を後押ししてきたキリスト教にも再考を迫るものとなるはずである。
心園記念事業会編『安炳茂著作選集1─民衆神学を語る』
安炳茂著作選集1『民衆神学を語る』
・心園記念事業会:編
・金忠一:訳
・かんよう出版
・2016年刊
・四六判519頁
・6,050円
最後に安炳茂の民衆神学を食の神学として再読することを試みたい。七〇〜八〇年代の民主化運動や現代の新自由主義の文脈で語られることの多い神学者だが、優れた神学書は意図せざる文脈においても深い洞察を示してくれる。
特に本書の「食卓共同体」の議論は示唆に富む。エデンの園にあった食べてはいけない果実は「誰も私有化することのできない公的なもの」を意味し、神も「大地も天も海も全て公」であるから、「共に労働して生産した全ての食べ物も公的なもの」である。「ところが、この公、すなわち取って食べてはならない木の果実が、容赦なく私有化され、独占化される過程が人間の歴史の罪悪化」「公を私有化することがすなわち堕落であり罪」だと理解するからである。
この私有化がキリストのからだとしての食卓共同体を不可能にすると主張する安の議論は、上記の二冊で示される人間自身の共同性や食の公共性の問題提起を先取りしている。三冊あわせて読むことで、「キリスト教と食」というテーマは神学的にも深められるはずである。
植木献
うえき・けん=明治学院大学教養教育センター准教授