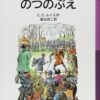セクシュアリティを理由に教会から排除されることがなくなることを目指して活動する「約束の虹ミニストリー」(寺田留架代表)が、2015年の設立から10周年を迎え、5月17日から22日まで、教文館(東京都中央区)3階のギャラリーステラで企画展「教会とセクシュアルマイノリティ――イエスさまと私たちの歩み」を開催した。
「約束の虹ミニストリー」は、セクシュアルマイノリティ(LGBTQ+)であるクリスチャンが安心して話し合い、祈り合える場所としてスタート。この10年、教会の中で傷つき居場所を失っていた当事者たちのために、既存の教会があらゆる人にとっての居場所になるために何が必要か、「虹ジャム」と名づけた交流会を中心に、非当事者であるアライ(支援者)の人々と模索を続けてきた。コロナ禍以降は主にZoomでの礼拝を通して、教会としての役割も担ってきた。
17日に行われたトークショーには、代表の寺田さんのほか、中心メンバーである川口弾さん、早川かなさんが登壇。お互いの出会いから、これまでの歩みを振り返り、虹ジャムの「グラウンドルール」として大事にしてきた「プライバシー保護を意識する」「多様な人がいることを意識する」「なんでも話せる雰囲気を皆で作る」の3点について、実体験や運用上の課題などを分かち合った。
後半は、アライとして「約束の虹ミニストリー」に参加してきた飯田るつ子さん、新井健二さんもトークに参加。それぞれが「虹ジャム」に関わるようになった契機と、アライとして伴走する難しさなどについて語った。
30年前、カミングアウトされたことを機に親しい友人と疎遠になってしまったという苦い体験を持つ飯田さんは、3年前に「虹ジャム」の存在を知って以来、ほぼ欠かさず参加するようになった。牧師として「虹ジャム」に参加する中で、「教会とは本来どうあるべきかを学んだ」と話す新井さんに対し、早川さんは「教会には行けないがここなら……」と来てくれる参加者がいたことを紹介し、「辛い時こそ行きたいと思う場のはずなのに、しんどいと行けない教会って何だろう」と疑問を呈した。
アライを名乗ることについての葛藤についても各々の体験から率直に意見が交わされ、川口さんは「アライとしてのアイデンティティが先行し、アライであることを目的化するのではなく、個々人の置かれた固有の状況から限られたリソースで何ができるかを考えることが大事ではないか」と強調。寺田さんは「知ろうとすることが第一歩。隣り人になることがアライの本質。世界中のすべての人の隣り人にはなれないが、身近な人の隣り人になる感覚でアライを目指してほしい」と呼び掛けた。
会場では「セクマイクリスチャン文化祭」も開催され、「信仰×セクシュアリティ」をテーマに募集したイラスト、漫画、詩、短歌、映像など、思い思いの作品が展示された。期間中は牧師、信徒を含む多くの関係者が会場を訪れ、バラエティ豊かな展示に見入っていた。
次回の「虹ジャム」は5月29日、午後8時から「虹ジャム礼拝」として行われる。詳しくはブログ(https://ameblo.jp/niji-min/)を参照。