わたしたちが祈りささげる雰囲気は暴力が蔓延している場所とは対照的だが、神の国の存在は議論対象外の現実的なものとして書かれている。神の国は「文明的な」場所で、礼儀正しく信頼に足る場所である。わたしたちの経験の中に独占的に「ここに」あるのではなく、特質上にはそこにあるのだが。(報道されることは例外なのだ、が)この神の国は未来への設計図ではない。また希望に満ちた願望や、適切な法律で実現可能な約束でもない。神の国はここにある。今ある。神はこの場所に住み、この世界に住む。神はわたしたちの国に時折来る観光旅行者ではない。神はこの場所に、この世界に住まわれる。神はわたしたちの海岸に時々訪れる観光客ではない。神はキャンプをするお方ではなく、住民としてここに住まわれる。そこに神の「国」がある。そこは暴力が起こる同じ場所でもある。それは、静かで人里離れた渓谷に神を探しに行く必要がないことを意味している。
アウグスティヌスはこの町のイメージを用いて、人間存在と人間の業の只中に、神が現存しご自身の御業を行っているという解説を展開している。神の道の歴史が、わたしたちの生き方の歴史に浸透している歴史でもある。アウグスティヌスは『神の国』を、アラーリック一世【西ゴート族の王、紀元410年にローマを占領した】と野蛮人の大集団が北方から雪崩(なだれ)込み、ローマ文化を破壊した時代、歴史で最も暴力的な時代の一つ、無秩序で粗暴な時代に書いたのだ。神の国とは現実逃避の神学ではなく、むしろ報道の形をとった祈りのようなものである。
川の噴水が喜びをまき散らす、
神の町を平静にしながら
いと高き神がいます
聖なるよく行く場所たまり場。
神がここに住めば、通りは安全だ。
神は夜明けとともに、
神はあなたがたの役に立ってくださる。
― 詩編46編4~5節

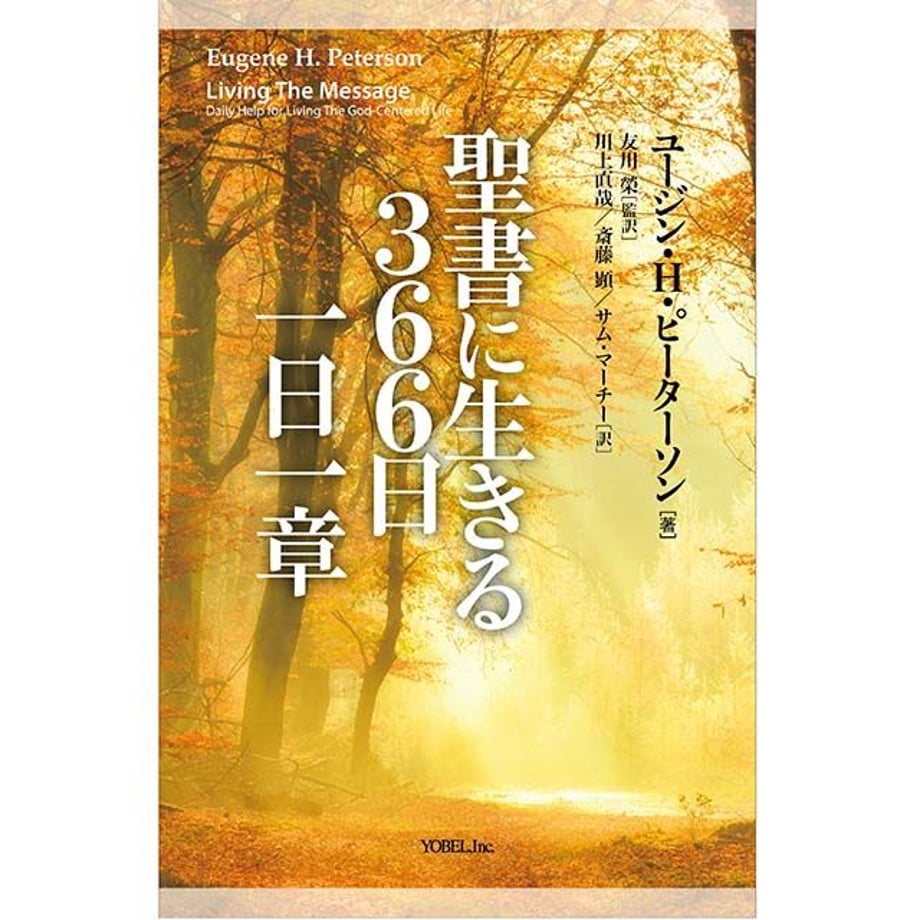 出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)
出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)