次はRex Stout著『Fer-De-Lance』の黙想。
レックス・スタウトが著した殺人シリーズがある。その主人公ネロ・ウルフは、太った私立探偵であって、聖職者ではない。しかしこの30年間、わたしも、わたしの友人たちも、この本を読むことが「キリスト教瞑想の現代的実践」となると思い、一つの譬(たと)え話として、この本を楽しんできた。ネロ・ウルフの物語は単なる探偵小説としてだけで、世間に広く知れ渡っている。これこそ、現代的な感性が人々を鈍麻(どんま)させている証拠である。ジョナサン・スウィフト【アイルランド生まれの英国風刺作家】のように、このシリーズの著者スタウトは、神学的明瞭さを帯びた作品として、この作品を著したのである。作者スタウトこそ、知的で内容豊かな探偵小説を著したベストセラー作家として、世間に認められるべき人物である。スタウトは実際にそう認められていた。しかし、彼が得た経済的利益に比べて、その内容への人々の理解はどうだろうか。今もなお、彼は完全に誤解されている。それは真面目で誠実な作家である彼にとって、実に屈辱的であるに違いない。
神学的意味を読み取れる読者には、その捜査の様子を少し見るだけで直ぐ「私立探偵ネロ・ウルフ」自体が現代世界の教会の在り方を表していると分かる。まず、ウルフは身体的に明らかな特徴がある。そこには教会と同類の何かが読み取れる。つまり彼は巨大なのである。読者は彼の「体重」に圧倒される。それは聖書的な意味での「栄光」の語源(ヘブライ語の「栄光」の語源は「よく知られている」)を思い起こす。他のどれにも優って、彼はそこに存在している。それは一目でわかる。彼を見落とすことは絶対に出来ない。 ―― 彼はとにかく「デブ」なのだ。教会はキリストの体である。キリストの肉体としての教会の大切さを強く主張することに加えて、キリストの体としての教会には「魅力が何もない」という意見が広まっている。キリストの体としての教会は、中傷とジョークの対象となっている。ここにウルフと教会の共通点がある。
ウルフの天才は、その知性とスタイルによって描き出されている。彼はお客におべっかを使わない。「コネ(contacts)」を手に入れようともしない。「ついでに言えば、ネロ・ウルフはコネという言葉を決して使わない。彼はかつて「コネ」という言葉がきちんと定義づけて説明されているということで、辞書を一ページずつ破って燃やしたことがある。」
ウルフは自分から出て行って捜査をしない。つまり彼はこの世のニーズに自分自身を合わせようとしない。物語が展開して行く、その中心にウルフはいる。彼は意思や黙想の中心にいる。彼は力や活動の中心にはいない。ウルフはキリスト教のスピリチュアリティーの理論的枠組み(パラダイム)を提供してくれる。そのスピリチュアリティーは寡黙で、打ち解けずシャイなのだが、ここぞという時に、巨大な存在感を示してくれる。ウルフは宣伝テクニックや広報プログラムを必要としない。彼はそこに存在して、必要とされている。なぜならば、この世に問題(殺人、その他の過激な犯罪)があるからだ。彼は黙想的な生活のモデルを提供してくれる。それはこの世では慕われていない。人から好かれるようにデザインされてもいない。それは素晴らしく堂々としている。中核的で、重要で、実際のところ、それが彼の天才の所以となっている。しかし、それは「あなたの好み」には合わないかもしれない。
以上全ての中に、現在の教会への批判が読み取れる。教会は今広報担当者によって引きずり倒されている。広報担当者たちは牧師となって、キリスト教の説教壇に登場し、教会を魅力あるものとし、擬人化し、感傷的なものとしてきたのだ。ウルフはそのような在り方に冷や水を浴びせる存在である。さらに、ウルフは自己弁護的な言辞(げんじ)を忌み嫌う。つまり、バルト主義者が示すとおりの「弁証学」への忌避がそこに続く。「この世界においてキリスト教が頼りになり効果的であること」を保証する努力を忌避する。ウルフはただこう語る。「教えてあげることも出来るよ。でも、どうだろうか。わたしはその価値が分かるが、あなたにはその価値が分からないだろうなぁ。」教会が自己弁護を試みる時、あるいは、世界が理解できる方法で自分のことを受け容れやすく宣伝する時に、霊的な命は安っぽくなる。ウルフはそのことを教えてくれる。
あなたがたが知っているように、
教会とはこの世の些末なことがらに関わない。
この世は、教会にとって些末なのだ。
教会はキリストの体である。
キリストは教会で語り、行動する。
教会を通してキリストが臨在し全てを満たすのだ。
―― エフェソの信徒への手紙1章22~23節
*引用される「聖書の言葉」はピーターソンさんの翻訳・翻案を訳したものです。

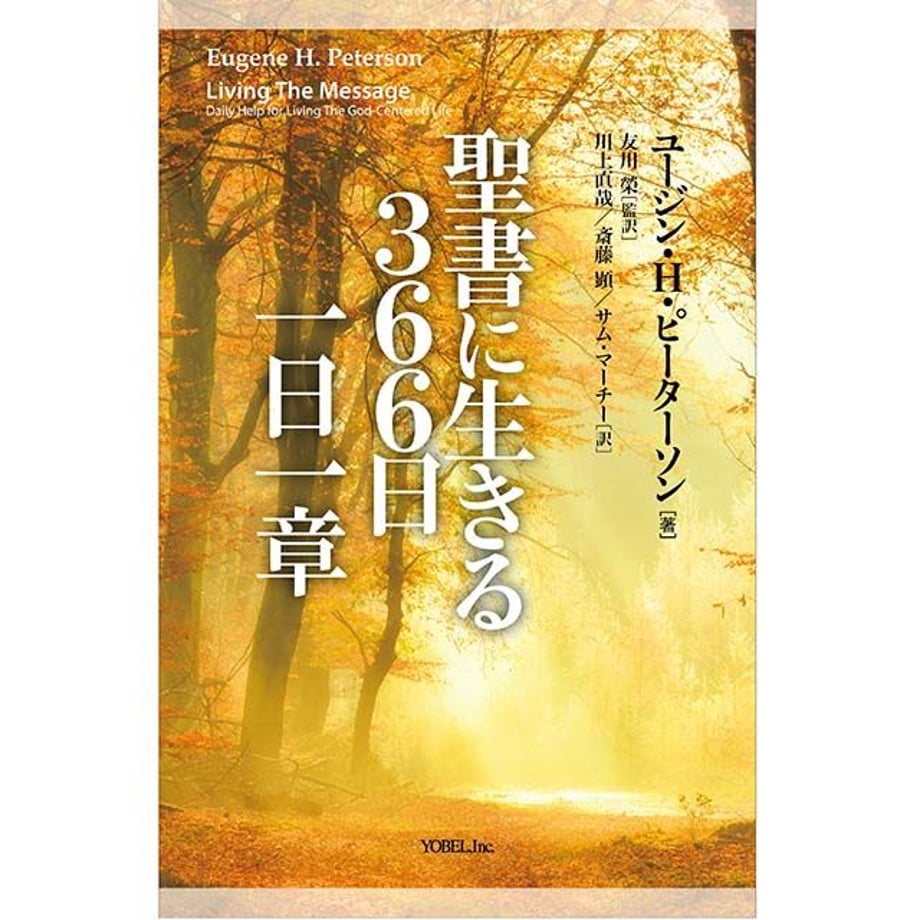 出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)
出典:ユージン・H.ピーターソン『聖書に生きる366日 一日一章』(ヨベル)