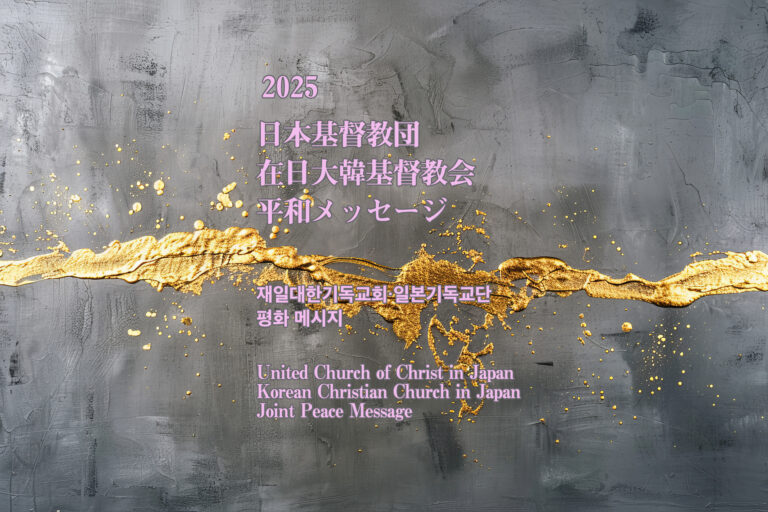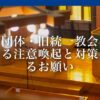日本基督教団(雲然俊美総会議長)と在日大韓基督教会(梁栄友総会長)は8月1日付で平和メッセージを発表した。
メッセージは、戦後80年を迎えるにあたり「自分の属する共同体や国家を越えて、帝国主義/植民地支配と戦争という暴力を導いた人間の愚かさによって苦悩と痛みを被ったすべての存在の痛みの声を聴く耳は備わっていたのかどうか」を顧みるとともに、60年前の日韓基本条約の意味を考察し、深い悔い改めが不在であったと述べた。また、「世界には自分とは違う痛みがある」ことを痛切に感じることができる者でありたいと願い、「ともに生きる」道を歩むキリスト者の道を模索することを提言した。最後に「『日韓』という国民国家のアイデンティティを背負い/背負わされつつも、私たちが背負うべき悔い改めの忘却という責任を引き受け、イエス・キリストの十字架の贖いに値する生を、『いま、ここ』から、再び、新たに、ともに紡いでゆきたい」と表明した。
メッセージの全文は以下の通り。
2025年 日本基督教団・在日大韓基督教会平和メッセージ
日本基督教団 総会議長 雲然俊美
在日大韓基督教会 総会長 梁 栄友
その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちは、ユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸にはみな鍵をかけていた。そこへ、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは、主を見て喜んだ。(ヨハネによる福音書 20:19−20)
自らが属する国民国家を代表する(represent)のではなく、「平和」が損なわれている世界にあって、イエス・キリストが吹きかけてくださる聖霊を受けた者として、小さくされ深い傷を負い、あるいは命を奪われた人々の声を再―現前する(re-present)者となることを望みます。
この地の表現者が「危機は単層でない」と発言したように、キリスト教界も「混沌とした」状況の中を生きているとの認識のもと、復活のイエス・キリストのからだには十字架の傷がありありと残っていたこと、つまり、復活は、十字架の死を「なかったこと」にしたのではないことをしっかりと胸に抱きつつ、イシューをカタログのように整理することからできるだけ離れて、危機の諸相/諸層に埋め込まれた問いをともに噛み締めたいと思います。
戦後80年をめぐって
1945年8月15日から80年の時を迎え、この日の名称が「敗戦/終戦/光復」と異なった言葉で表現されることの意味を、そして、その差異はいったい何によってもたらされたのかを噛みしめることができる私たちでありたいと思います。その際、私たちは、誰の痛みを受け止めたのか。自分の属する共同体や国家を越えて、帝国主義/植民地支配と戦争という暴力を導いた人間の愚かさによって苦悩と痛みを被ったすべての存在の痛みの声を聴く耳は備わっていたのかどうか、この時、深く顧みる者でありたいと思います。
日韓条約60年をめぐって
60年前に二つの国民国家の間に締結された条約の意味をともに噛み締めたいと思います。日本は植民地支配の「補償」という言葉を忌避し、「経済支援」という名分にこだわり、韓国は「経済優先」の必要に迫られ、ついには曖昧な妥協に至りました。このことによって、日本は歴史修正の勢いがつき、韓国は独裁政権の正当化に繋がったこと、そして、その後の分断をさらに深刻にしたことの意味を、また、「補償」ではなく「経済支援」という表現に固執したことにより、深い傷を追った個人の痛みが不問に付される道を築いてしまったことの意味を、ともに噛み締めたいと思います。その淵源には、朝鮮半島の北側を無視し、「朝鮮籍」として取り残された存在に対して、「煮て食おうが焼いて食おうが自由」との国家の意志が横たわっていたこと、そして「日韓」の双方にそのことに対する深い悔い改めが不在であったことを、ともに記憶したいと思います。
この地と彼の地に積み重なった戦争をめぐって
「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれた広島の原爆慰霊碑。「ベトナム戦争中に韓国軍が引き起こした虐殺事件に謝罪するため」に済州島の聖フランシスコセンターに建てられたピエタ像。自らを射抜く、この二つの碑が指し示す心の深さを、いま、この時、ともに胸に覚えることができる私たちでありたいと思います。併せて、朝鮮戦争を、この地の経済発展の契機として「特需」と認識してきたことへの深い悔い改めを共有するとともに、パレスティナなどで起きているジェノサイドを結果として見て見ぬふりをしてしまっている私たちが想像力を取り戻し、「世界には自分とは違う痛みがある」ことを痛切に感じることができる者でありたいと思います。
ヘイトをめぐって
在日コリアンをめがけたヘイト・スピーチやヘイトクライム、そしてクルド人に向けて最も過激な矛先を向ける敵意が存在します。その敵意を後押しするような国会議員の言説が湧出する危機を、ともに危機と明らかに認識したいと思います。しかるべき法的措置がなされることの働きかけをおこなうとともに、「ともに生きる」ことと、「誰かを排斥する」ことの分岐点はなぜ現れたのか、「ともに生きる」道を歩むキリスト者の道はどのように整えられるべきか、祈りのなかで、ともに模索する私たちでありたいと思います。この道は、いまも暴力にさらされている沖縄の民の苦悩や、原発事故の傷などなかったことにされつつあるように思われる福島の人々の痛みを、「はらわたがちぎれる思い」をもって共感された/「深く憐れまれた」(マタイ9:36)イエス・キリストのからだに連なる道であると信じます。
貧困と格差、蔓延する不遇感のなかで
物価の高騰、給与の目減り、就職氷河期を生きた人々の抑圧された生に見られるように、多くの人が、いままでになく明るい明日を予測できない不安を感じながら、「わたしだって可愛そうなんです」とつぶやくような社会に、私たちは生きています。そのなかで、蔓延する「自己責任」という言葉を、人々はいつのまにか内面化し、「ともに生きる」道を自ら遮断しているのではないでしょうか。SNS上に繰り広げられる薄っぺらな記号のような「コトバ」の氾濫のなかで、人々が敵意によって不安を満たすことが起きているとしたら、キリスト者の道は、そのような「コトバ」がもたらす不安の似非の「解消」ではなく、真の「平和」をもたらす、「いのち」の「ことば」を届けることであると信じます。
私たちは、いま、この時、イエス・キリストの洗足の身振り(ヨハネ13)をともに想起したいと思います。
生活の中で最も汚れた部位である足を洗うということ。それは、汚れた部位を指摘して非難し分断を深めるのではなく、その部位を洗い合うことによって、自らの汚れに気づき、悔い改めを忘却する身振りを離れて、新たな道に進むからだを整えることと信じます。「日韓」という国民国家のアイデンティティを背負い/背負わされつつも、私たちが背負うべき悔い改めの忘却という責任を引き受け、イエス・キリストの十字架の贖いに値する生を、「いま、ここ」から、再び、新たに、ともに紡いでゆきたいと思います。
2025.8.1