他宗教は改宗の対象ではなく、対話と共存、協同の対象であること、そのような宗教の多元状況を前提とした布教のあり方を、諸宗教の心ある指導者たちは模索している。自らの宗教の絶対性を前提とした神学のあり方そのものが問われていると前回書いた。
真っ先に問われるのは、キリスト論、とりわけ贖罪論であると思われる。このことを1931年に英国で出版されたグスターフ・アウレン著『勝利者キリスト――贖罪思想の主要な三類型の歴史的研究』(佐藤敏夫氏他による邦訳の出版は1982年)を手がかりに考えてみたい。アウレンは、この書において贖罪思想の主要な三類型として古典説、客観説、主観説の三つを設定している。
古典説とは新約聖書や古代教父そして宗教改革者ルターなどに認められる贖罪論で、その特徴は神と悪魔の二元論的闘争、その闘争の勝利者としてのキリストである。そしてこの贖罪論においては贖罪=救済であるとされる。
客観説はラテン説とも呼ばれ、中世の神学者アンセルムスの『クール・デウス・ホモ』(神はなぜ人となったか)において体系的に示され、プロテスタント正統主義に受け継がれて現代に至る主流派の贖罪論である。この贖罪論においては贖罪>救済とされる。すなわち贖罪は、それを救済として信じようと信じまいと絶対に客観的な事実である。十字架におけるキリストの贖罪死をまったく知らない(その救済に全く無自覚な)人のためにも、キリストは死なれたのだと考える。
この客観説に対するいわば反動が主観説で、その萌芽は中世のアベラルドゥスに認められるが、近代の神学者シュライエルマッハーにおいて代表的に展開されたといわれる。贖罪と救済の関係は、贖罪<救済となる。
「古典的贖罪思想が支配的なところでは初期の教会でもルターでも等しく、救済は贖罪であり、贖罪は救済である。ラテン説においては事情は異なる。贖罪が救済に先立つものとして、それに対して先行的なものとして、それに続く救済の過程を可能ならしめるものとして扱われる。しかしシュライエルマッハーは順序を逆にする。救済(精神的生における変化)がまず最初に来、贖罪(和解)がそれの完成として続く」(邦訳161頁)。
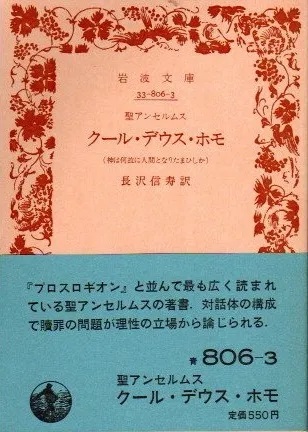
アウレンの願いは、主流派の客観説に対して古典説を復興することであり、客観説に対する反動に過ぎない主観説は、贖罪論としては論外である。
客観説の強みは「自分が信じられるか信じられないか」といった主観的な思いを度外視することができる点である。「主観的に信じられるかどうかは問題ではない。キリストはあなたが信じようが信じまいがあなたの罪のために死なれたのである。その事実を伝えることこそが伝道だ」ということになる。
その背後にあるのは、キリスト教の普遍性(絶対性)に対するゆるぎない確信である。少なくともキリスト教世界において20世紀の初頭(第二次世界大戦前)までは、多くのキリスト教徒がこの確信のもとにイエス・キリストの世界宣教令(マタイによる福音書28章19節)を文字通り信じ、終末論的には仏教徒もイスラム教徒もキリストのご支配に入ることを信じて非キリスト教世界に布教をしていった。
しかし、現在、原理主義的な一部の教派集団を除いて仏教やイスラム教世界をキリスト教化するというビジョンを本気で持っているキリスト教徒は、どれくらいいるだろうか。むしろそれを明言するか否かは別として、キリストの贖罪によらない救済も容認する(仏教徒は仏教徒のままで、ムスリムはムスリムのままで救われる)多元主義的な救済観が現実的であることを、多くの人が認めつつあるのではないだろうか。シュライエルマッハーの主観説贖罪論は、そういう現実を踏まえ再評価される可能性がある。(つづく)

川島堅二(東北学院大学教授)
かわしま・けんじ 1958年東京生まれ。東京神学大学、東京大学大学院、ドイツ・キール大学で神学、宗教学を学ぶ。博士(文学)、日本基督教団正教師。10年間の牧会生活を経て、恵泉女学園大学教授・学長・法人理事、農村伝道神学校教師などを歴任。





