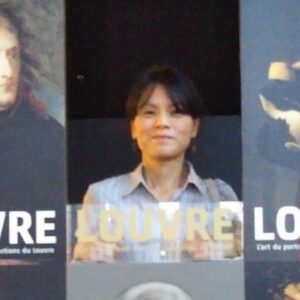日本キリスト協議会(=NCC、東京都新宿区)が主催する公開学習会「日韓条約60年とエキュメニカル運動――その歴史と課題」(5回シリーズ)の第1回目が6月7日、明治学院大学名誉教授の徐正敏(そ・じょんみん)氏を講師に招き、日本キリスト教会柏木教会(東京都新宿区)とオンライン(Zoom)によるハイブリッドで開催された。対面26人、オンライン29人が参加した。
「日韓条約(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)」の締結から今年で60年。1965年に冷戦体制下で結ばれた同条約は、当時の韓国キリスト者たちから日本の侵略精神の継続として反対の声があがっていたが、NCCはその声に向き合わなかった。その後NCCは、在日大韓キリスト教会の民族差別との闘いや韓国民主化運動の闘いに連なっていくようになるのだが、なぜこの時期反対の声に向き合うことができなかったのか。5回にわたる公開学習会では在日・日本・韓国のキリスト教関係史を振り返りながら、日韓条約の何が問題なのか、キリスト教会の課題は何かといったことを改めて検証していく。
第1回では、日韓キリスト教史を専門とする徐正敏氏が「戦後日韓キリスト教関係の変化――エキュメニカル運動と『東京発1973年韓国キリスト者宣言』を中心に」と題して講演を行った。講演では、近代的なエキュメニカル運動の流れに触れた後、戦前の日韓キリスト教関係について明らかにし、その関係が戦後どのように変化したかを1973年に東京から発信された「韓国キリスト教宣言」をとおして説明した。

徐正敏氏=6月7日、日本キリスト教会柏木教会(東京都新宿)で。
近代的なエキュメニカル運動は、アフリカやアジアに派遣されたアメリカの各教派の宣教師らが、別々の教派であっても現場では連合してキリスト教を伝えようということで生まれた。徐氏はこれを「宣教エキュメニズム」と呼んでいる。日本と韓国のキリスト教は、この「宣教エキュメニズム」の流れを背景にして生まれてきたが、歩む道は違っていた。日本の朝鮮半島植民地化政策は、日韓キリスト教に大きな葛藤を引き起こしてしまった。
敗戦直後、日本のキリスト教会の説教は、戦争の福音から平和の福音へと変化した。しかし、変更したことに対する論理的な説明はなかった。1947年に日本基督教団が「日本のクリスチャンが一致団結して日本を復興させていこう」と表明したが、そこにも植民地支配への反省の言葉は一言もなかった。「なぜ教会の責任を告白しないのか?」と多くの非難の声があがったが、日本の教会は20年間沈黙を貫き通した。日本キリスト教史を常にポジティブに読み解いている徐氏でさえも「戦後20年の日本キリスト教会の動きが、その後の日韓キリスト教の関係に大きな影を落としている」と指摘する。
徐氏が戦後の日本キリスト教会の歴史で最もシンボル的な出来事として、1967年に発表した日本基督教団の第二次大戦下における戦争責任についての告白をあげる。これは当時の同教団総会議長であった鈴木正久の名前で出されたことで、満場一致によって出された告白ではないと言われている。それでも徐氏は、「満場一致よりも反対側の意見がないというほうが嘘だと思う。葛藤の中で発表した告白のほうが真実性がある」とポジティブに受け止めていることを伝え、こう続けた。
「この告白がこの場だけの発表であれば、私も絶望する。日本のプロテスタント教会は言葉だけで実践的でないとよく言われる。しかし私は、この告白から実践が生まれてきたと思っている。1967年以前と以後では日本キリスト教は変化した。それまでは日本のエリートたちに目を向けてキリスト教を広げていくことを目標にしていると感じられたが、この戦責告白を出してからは、社会のマイノリティたちと共に歩んでいくことを目標とするようになった。具体的には在日コリアン、被差別部落、そして沖縄への関心がここから積極的になったのではないか」
日本のキリスト教が変わっていったことを、その後に発表された声明などからも明らかにした。1995年1月にはNCCが「『戦後50年』のときにあたって」と題しての声明を発表し、国家の植民地政策、東アジアに対する侵略に教会が沈黙と協力していたことに加え、関東大震災における朝鮮人の虐殺にも触れ真摯に反省を述べている。さらに同年4月には「日本の戦争責任と戦後責任に関する日本キリスト協議会声明」を発表。その中では戦後責任の不履行などに対する相対的反省、戦後責任遂行に対する努力が誓われている。
韓国強制併合から100年となる2010年には、日韓のキリスト教協議会(NCC JとNCCK)が共同声明を出し、1910年の日本の武力による日韓併合は無効であることを正式に表明した。また1995年には、徐氏が教鞭をとっていた明治学院大学においても「明治学院の戦争責任・戦後責任の告白」が学院長名で出された。そこに関わった人たちの名前を挙げながら教育機関としての戦争責任を告白。学院長名での声明は、1967年の日本基督教団と同じと言えるが、この告白も歴史的には大きな意味があると徐氏は力を込めた。
戦後の日韓キリスト教関係での最も注目すべきこととして徐氏は「東京発1973年韓国キリスト者宣言」をあげる。これは、韓国キリスト教民主化運動史における最初の神学的宣言および信仰告白で、1973年、朴正煕軍事独裁政権下の韓国で秘密裏に流布され、その後世界で発表された。 教会が先頭に立って政治に働きかけていくことは、1919年に発生した反日独立運動(3.1独立運動)からすでに行われていた。ただ、そういった運動を支える神学的な論理はできていなかった。「東京発1973年韓国キリスト者宣言」では、キリスト者が民主化運動に参加することへの神学的、信仰告白的基礎を示し、それにより対外的説得力を確保した。そうすることで、世界教会との協力と連帯を実現させることができた。
宣言の作成に関わったのは、池明観氏、金容福氏、呉在植氏の3人。KCIA(大韓民国中央情報部)が目を光らせる中、韓国キリスト教協議会の名前で東京から発表し、最後まで誰が書いたかわからないようにした。それでも、日本語版と韓国語版を作成した池明観氏は、20年間1度も祖国に帰ることができなかった。それほど同宣言の発表は危険なものだった。そんな危険の中でも同宣言を出すことができたのは、日韓条約に反対し韓国民主化運動の闘いに連なる日本のエキュメニカル運動の助けがあったからだという。
池明観氏はその後も日本のキリスト者から支援を受けながら、韓国での人権抑圧や民主化運動の実態を世界に伝え続けるのだが、徐氏は池明観氏から聞いた言葉を明かした。
「日韓の境界を生きることができたのは、自分の能力によるものではなく、ただ両国間に河の水のごとく流れる友情の波間の上に浮かび、揺られる小さな船のようなものに過ぎなかった」
日韓の関係を「友情」と表現する池明観氏の言葉は、日韓条約締結以降エキュメニカル運動を進めてきた日本キリスト教にとっては大きく心に響く。ただ、それぞれの教団教派を見た時、あるいはキリスト教を全体で見た時、エキュメニカル運動の理想とはほど遠いと思わされることもあると徐氏は無念さをにじませた。それはキリスト教の危機とも言えることで、今後日韓におけるキリスト教の立て直しが必要であることを示唆して講演を締めくくった。
「NCC公開講演会」の次回以降の予定は以下の通り。
第2回 7月5日(土)講師:山口明子氏(1966~1990年NCC幹事)
第3回 9月27日(土)講師:大久保正禎氏(日本基督教団西方町教会牧師)
第4回 10月25日(土)講師:金迅野氏(在日大韓・横須賀教会牧師)
第5回 11月22日(土)「わたしたちの課題は?――4回の講演を聞いて」
※問い合わせ Eメール=general@ncc-j.org。℡03-6302-1920。