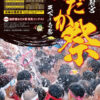5月は、結婚式を挙げる人が多いそうだ。結婚情報誌『ゼクシィ』が例年行っている「結婚トレンド調査」の2024年版によれば、結婚式開催にあたって圧倒的に人気なのが11月、その次に10月で、差を付けずに5月という順である。
現代の人々は、どのような形で結婚式を挙げるのだろうか。「古風で」「伝統的な」結婚式を求める人々は、神前式を選ぶことが多いだろう。神前式は、結婚式場やホテル、神社において神職が行う結婚式で、1960年代に普及して以降、広く人気を博した。1990年代以降にキリスト教(教会)式が急増して以降は少数派となったが、現在も、多くの神前式場が「日本ならではの伝統的な形式で」という宣伝で集客し、和装に憧れを持つカップルや、外国人カップルなどからも支持を得ているようである。
加えてもう一つ注目したいのは、2000年代以降に存在感を示し始めた人前式である。キリスト教式、神前式、仏前式が、聖職者を通して神仏に結婚の誓いを行うのに対し、人前式は、その場に参列している家族や友人に向けて、誓いを立てるものである。人々に対してのみ誓いを立てるという点以外は、儀礼内容は基本的にその他の形式と変わらない。大体の場合、新婦は白いウェディングドレスか色打掛、あるいは白無垢を、新郎はタキシードか紋付袴を着る。入場を終えると、郎婦が誓いの言葉を述べ、指輪を交換し、結婚証明書に署名、ゲストが拍手などで結婚を承認し、退場、という流れだ。宗教色が希薄で、自らのオリジナリティを反映させやすいことから、「新しい」「自由な」という印象が持たれており、若者世代に人気のようである。
神前式は伝統的で、人前式は現代的、という見方はどれだけ適切なのだろうか。実は、神前結婚式自体の歴史はそこまで深くはない。神前結婚式が有名になったのは、1900年にのちの大正天皇が宮中三殿の神前で結婚の儀を行ったのがきっかけだとされている。これを模す形で、現在の東京大神宮が、庶民に向けた神前結婚式を考案し、広く知られるようになったことで、一般に普及した。伝統的だとして支持を得ている神前式は、実のところ近代以降に創出された比較的新しい形式なのである。
では、それまでの結婚式はどのようなものだったのだろうか。ほとんどの場合は新郎の自宅で祝言が行われるという形態であった。一部では婚礼において神の存在が意識されることはあったものの、神職がかかわることはなく、身内の者だけで執り行われていた。祝言の内容は地域や時代によって大きく異なるが、基本的に近世以降は、新婦が嫁入り道具を持って新郎宅へ赴き、盃を交わし、集まった身内の者とともに祝宴を挙げていた。長らく庶民の間で行われていた婚礼儀式の祝言は、実は現在「新しい」と考えられている人前式の方に、より近い形態なのかもしれない。
以上のことから、現在行われている結婚式は「伝統的/現代的」の二元論には一概に落とし込むことはできないということが分かる。伝統的だとされている神前式は近代以降に創られた形式で、反対に現代的だとされている人前式には過去の祝言に通ずる要素を見出せる。結婚式に限らず、私たちが「伝統的だ」と認識しているあらゆる儀礼的な行いは、実は近代以降に新たに生まれたり、それまで存在していたものを適宜修正・調整したりして構築されてきたのである。だからこそ、ある宗教的・文化的事象を考える際には、その起源や歴史的背景だけでなく、それがいかに人々によって〝正統なもの〟として信じられ、共有され、形作られてきたのかという過程にも目を向ける必要があるだろう。

牧田小有玲
まきた・こうれ 1994年静岡県生まれ。慶應義塾大学院社会学研究科博士課程在籍中。論文に「神社神道で構築されるジェンダー規範についての一考察 ―女性神職に関する言説分析から」(『宗教学論集』)がある。