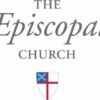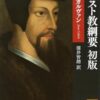「宗教から見る中東の戦争と平和」をテーマとするシンポジウムが、(公益財団法人)国際宗教研究所によって開催された。発題者は、⼭本健介(静岡県⽴⼤学国際関係学部講師)、藤本龍児(帝京大学文学部教授)、⽝塚悠太(東京⼤学⼤学院博⼠課程)の各氏。パレスチナ・中東地域の紛争は、政治の観点から語られることが多いが、本シンポジウムでは「宗教から見る」。昨今の国際的な関心を反映して、オンラインを含め約200人の参加者が一堂に会した。
最初に登壇したのは、エルサレムや聖地の研究を行ってきた山本氏。「パレスチナ問題とイスラーム:『宗教紛争』の虚像と実像」と題して、「パレスチナ問題=宗教紛争」というイメージが正しいのか否か、宗教がらみと捉えられがちな中東情勢を、専門家の立場から解説した。
「一般に、パレスチナ問題の話をするとき、ユダヤ教とキリスト教の話をしてから現代の話をすることが多く、この問題は聖地の正しい持ち主は誰なのかをめぐる宗教間のいがみ合いだと考えられている傾向がある。確かに、聖都エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラームに共通する聖地だが、パレスチナ問題において、宗教は根本原因でも本質的な構成要素でもない」
山本氏はパレスチナ問題における宗教の役割と影響を、大きく三つに分けて検討。宗教が、権利主張の論理構築や行動の動機づけ、大衆動員と自己正当化に重要な役割を果たしてきたことを、事例を挙げて論証した。
「人は自らの主張・要求の内容を組み立てる基礎として、啓典や宗教的な故事を用いる。ユダヤ教やキリスト教が宗教を持ち出して何かいうと、外部の者はそういうものなのだと思い、それは変えられないのだと考えるが、必ずしもそうとはいえない。紛争当事者が構築した言説であることをわかっていないといけない。『宗教に基づく主張』はあくまで紛争下の文脈における構成物なのだ。また、為政者が人びとへの呼びかけや、自らの行動を宗教的に演出するために宗教的な語彙や象徴を利用することもある。例えば、ハマスは軍事作戦に宗教的な語彙をつけて呼称とした。2012年の第二次ガザ戦争は『焼け石の礫の戦い』と命名されたが、これは『クルアーン』の『象章』にある言葉から取ったものである。宗教的雰囲気を出すことでイスラーム世界全体にアピールすることもできた。宗教の政治利用であり、実際の行動と宗教の結びつきは極めて表層的になる場合もある」
宗教の相違は紛争の原因ではないが、それでも宗教的な側面や要素を無視することはできないという考え方は、すでに研究者の間では共通理解となっている、と山本氏。現状を整理し、「宗教の政治利用」が効果を発揮する背景こそが紛争解決上の根本課題であるとした。
続いて登壇したのは藤本氏。実は、加藤喜之氏(⽴教⼤学⽂学部教授)が「⽶国福⾳派とキリスト教シオニズム」と題して発表する予定だったが、体調不良のため会場に足を運ぶことができず、急遽、同じ分野を専門とする藤本氏が登壇することとなった。あらかじめ加藤氏が用意した原稿を、藤本氏が要約して伝え、あわせて藤本氏自身の発表「宗教保守と中東政策の観方:2025年以降の世界に向けて」を行った。
藤本氏は「ガザ侵攻で世界中からイスラエルへの非難が巻き起こる中、アメリカのイスラエル支持は変わらない。よくトランプ大統領や共和党のイスラエル支持が強調されるが、バイデンも『私はシオニストだ!』と公言するほどイスラエルを支持してきた」とした上で、「なぜイスラエル支持は揺らがないか、それが問いとなる。さて、アメリカの宗教を捉える際に、教派で捉えることがあるが、各教派も分裂しており『同じ長老派だから』などと考えると大きく間違う。福音派は重要であるものの一枚岩ではなく、その主張も多種多様。まず大枠でとらえるために、私は『宗教リベラル』と『宗教保守』という分け方が適切であると考えている」と述べた。
また豊富な資料をスライドで提示しながら、「宗教リベラル」と「宗教保守」の相違点、それぞれの特徴、政治との関わりなどを概説。さらに、イスラエルにおけるアメリカ大使館移転問題を取り上げた。テルアビブにあったアメリカ大使館を実際にエルサレムに移転すると宣言したのは、第一次トランプ政権下の2017年。識者たちは「口先だけで実現されないだろう」「実現されれば第五次中東戦争が勃発する可能性すらある」などの分析をしていたが、さっそく2018年、実施された。アメリカは中東に対する最大の軍事支援国でもある。
「イスラエル支持はトランプとその周りの人たちだけが推進している政策ではなく、民主党時代から変わらない方針だった。より大きく見れば、アメリカ建国前から続く歴史的、宗教的な重さがある。もちろん、宗教保守をふくめ国民はガザの状況には心を痛めている。しかし、終末観や歴史観、あるいはイスラエルが中東の民主主義国であること、対テロ対策など、支持の背景は一様ではない。かつては近代化によって宗教の社会的影響力は低下するという考え(世俗化論)が支配的だったが、必ずしもそのようには考えられなくなってきた。こうした観方を社会哲学では『ポスト世俗化』という。アメリカの現状を反動的な宗教勢力のせいだと考えると見誤る。この半世紀間でみても、繰り返し宗教の衰退が指摘されてきたが、むしろ宗教の影響力は形を変えつつも世界的に無視できなくなってきた。科学的世界観が広まれば宗教的世界観が衰退する、という観方はもはや通用しなくなっている」
最後に、イスラエルへの留学経験のある犬塚氏が登壇。「イスラエルの宗教右派とガザ:⼊植地撤退の歴史から考える」と題して、宗教的右派集団(宗教シオニズム)がイスラエルの歴史的・社会的変化とどのように関わってきたのかを論じた。イスラエルはユダヤ国家と規定されており、宗教と国家には独特の結びつきがある。人口の約81%がJewishとされるが、そのうちで最も多いのが、ユダヤ教を生活の中であまり重要なものと考えず、シナゴーグ(ユダヤ教の会堂)にもほとんど行かない世俗派と呼ばれる人たちである(約40%)。次いで、戒律の一部を文化や伝統として選択的に実践する伝統派(23%)がおり、その後に、戒律を遵守するが、兵役や労働も行う宗教派(10%)、戒律遵守を重要視し、伝統的な生活を維持するために社会から距離を取る超正統派(8%)が続く。宗教的右派集団とは、このうちの宗教派と重なる。
「宗教シオニズムとは、テオドール・ヘルツルが開始したシオニズム運動(ユダヤ人の国家建設を求める民族運動)に参加した宗教者の流れのこと。初期の宗教シオニストたちは、シオニズム運動や国家建設を救済とは結びつけず、あくまでユダヤ人の状況改善を目指す運動として提示していた。だが、第三次中東戦争(1967年)の勝利と領土拡大を受けて、宗教的な救済が近いという感覚が強まり、救済に向けたプロセスの進行のために聖書に書かれた領土をすべて獲得しようというイデオロギー(大イスラエル主義)が積極的に提示されるようになる。その中でグーシュ・エムニームと呼ばれる入植活動を繰り返す集団が現れた」と犬塚氏。
2005年、入植を進めていた当時のシャロン首相が突如、ガザからの一時撤退を行い、シオニズムが救済のプロセスと結びつくという思想が弱まることもあった。しかし2024年10月、「ガザ入植への準備会議」が開かれ、政治家や閣僚も参加。こうした再入植論では、かつてのような宗教的な動機ばかりではなく、安全保障という観点が強調されており、犬塚氏によれば「以前とはロジックが変わり、政治的影響力も増加している」という。停戦合意は、なお予断を許さない状況にある。
3氏による発題に対し、コメンテーターとして、松井ケテイ(清泉⼥⼦⼤学地球市⺠学科教授)、大河内秀人(特定非営利活動法⼈パレスチナ⼦どものキャンペーン代表理事)の両氏がコメント。宗教間対話が肝要である、宗教の果たす役割が大切であるといった見解が示された。コメントを受けて発題者が応答後、全体討議が行われた。
最も多くの質問を受けていたのは山本氏。「パレスチナ問題は宗教間の対立が原因ではない」と述べたことが、「パレスチナ問題に宗教は関係ない」と読み替えられて問われたり、「宗教的要素はもっと大きな位置を占めているのではないか?」という質問も寄せられた。山本氏は、「パレスチナ問題は宗教問題ではないが、シオニズム自体に宗教が組み込まれていることは事実。ヘルツルは、何もこの土地でなくても、アフリカに建国してもいいのではないかと言って、批判されたことがある。建国(帰還)する先はイスラエルしかないと彼らは考えるからだ。だから、シオニズムが内包している宗教性はどうなんだ、という点はもっとも。しかし、実際の宗教シオニズムは政治的に上がってきたものである。ハマスは宗教的な戦闘名をつけなくてもイスラエルを攻撃できるのに、これまでずっと宗教的語彙を利用してきた。『クルアーン』の中の『象書』は、ムハンマドが生まれたころに戦争で象を使っていたことにちなむ名だが、そこから語彙を取ってきたのは、あまり深い思いを込めた感じではない」と応じた。
歴史的にユダヤ人はショアー(一般には「ホロコースト」と呼ばれる)を経験しながら、なぜ強硬な姿勢を崩そうとしないのかとの質問に対し、犬塚氏は「彼らはポグロム、ショアーと、歴史的に迫害を経験してきた。そのため自分たちのことは自分で守らないといけないという意識が非常に強い。現地のユダヤ人と話していると、そうした歴史に基づく不安を持っていることが強く感じられる。我々からすると、なぜそんなに強硬なのだろうかと思ってしまうが、そうした意識が強く存在していることにも目を向けていく必要がある」と答えた。