私が住む地域の子ども会は、小学校の登校班編成に必要なため、ほぼ強制加入となっています。地域コミュニティとのつながりを作ることや、地域の子どもたちのための協力は必要なことですから、それは良いでしょう。小学生が安全に登下校できるように助け合いつつ、ゆるやかなコミュニティとしてつながっていることが、私を含め多くの保護者たちの願いでしょうから。
けれども、任期1年の役員となって初めて知ったのですが、子どもたちの見守りをする朝旗当番の調整に加えて、定期的に開催される子ども向けのイベントのお手伝いをすることも役員の役割でした。私は割と時間に柔軟性のある働き方をしているので良いのですが、共働きが当たり前であり、働く曜日や時間帯も多様である現代の日本社会で、これまで行っていた通りのイベントをいくつも行い続けることに無理を感じました。私よりも責任のある役割を担う方は、なぜか自治会のお手伝いまで絡んでくるというあり様でした。そのため、地域の子ども会に関しては、教会に通う同世代の方々からも不満や愚痴が聞こえてきます。少なくとも、現役の子育て世代が願っている形で地域コミュニティが機能していない現状といえるのかもしれません。
そのような地域の現状に、もしかしたら教会は多少なりとも貢献できるのではないかと、感じた出来事がありました。1月の第3日曜日の礼拝後に、小山教会ではお餅つきをしました。クリスマス関連の行事から始まった一連のイベントの最後の締めくくりです。小山教会はこれまで新成人の方がいる場合、そのお祝いとして餅つきをしてきました。ここ数年そのような機会もなかったのですが、教会に集う子どもたちに教会でやってみたいことがあるか尋ねてみたところ、餅つきと答えてくれた子がいたので、昨年1月、久しぶりに餅つき会を開催しました。久しぶりの開催は小山教会の方々にも好評でしたし、何よりも地域の方たちを誘いやすいイベントでしたので、今年は地域の方たちにオープンなイベントとして開催しました。餅つきには、教会の子どもたちの保育園や小学校の友だちやその家族が足を運んでくださいました。子どもたちにとっても、餅つきというイベントは、自分の友だちを誘いやすいイベントだったのでしょう。
お餅をひと通り楽しんだ後、子どもたちが遊ぶ傍ら、礼拝堂で保育園の保護者の方たちとゆっくりお茶をして過ごしました。普段は、なかなか保育園の保護者の方たちと話す時間はありません。子どもの送り迎えですれ違い際に簡単にあいさつを交わすくらいですので、ゆっくり一緒にお茶をしながら過ごすのは、とても貴重な時間でした。それは私や妻だけでなく、他の保護者の方たちも感じてくださっていたようで、教会が提供する空間を地域コミュニティの一つとして楽しんでいただけた時間でもありました。それは、現在の子育て世代が願っている形としてうまく機能していない既存の地域コミュニティが手を伸ばせずにいる部分を、教会が補える可能性のように思えました。
肩の力を抜いて、純粋に人との関わりを楽しめる場所を提供できる、コレカラの可能性が教会にはあるのでしょう。私たちの教会も地域コミュニティの一つとして、地域の方々が子育てや子どもたちの進学のこと、親の介護やお墓のことなど、人生のさまざまなステージで抱える悩みを気軽に相談できる場所を少しでも作っていけたらと願っています。
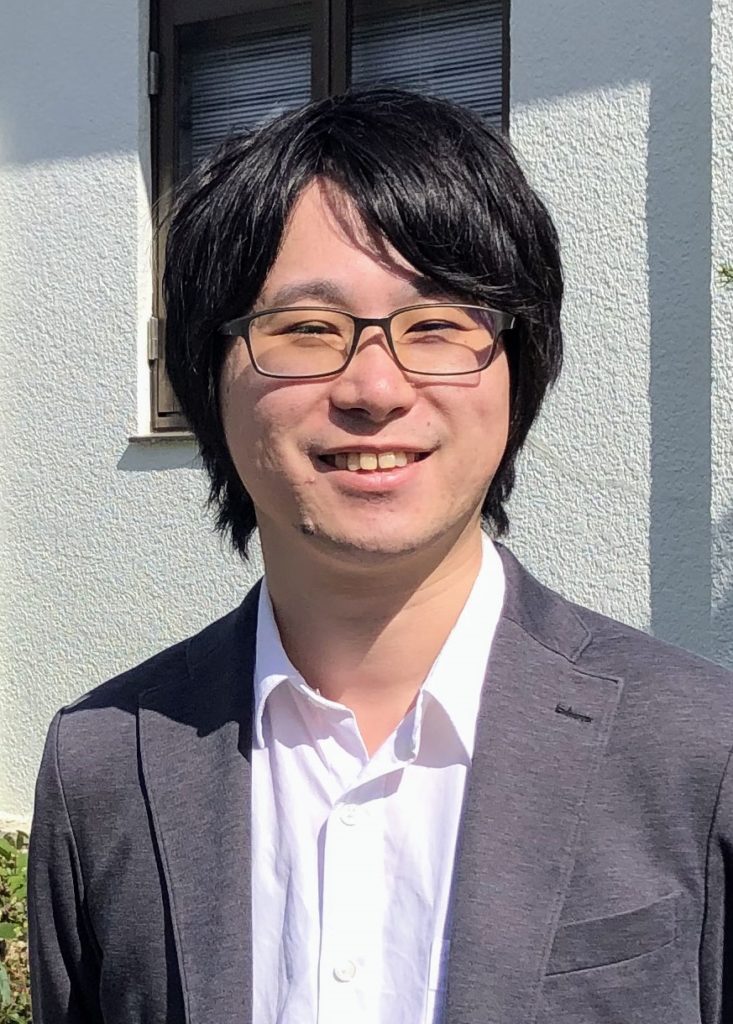
いなば・もとつぐ 1988年茨城県生まれ。日本大学、日本ナザレン神学校卒業後、数年の牧会期間を経て休職し、アジア・パシフィック・ナザレン神学院(フィリピン)とナザレン・セオロジカル・カレッジ(オーストラリア)に留学。修士号取得後、日本ナザレン教団小山教会に着任。趣味は将棋観戦とネット対局。




