今年の復活日は4月20日である。北日本では復活の喜びと共に満開の桜を楽しむことができるだろう。私の住む神戸では、葉桜の新緑の輝きから命の意味について思いを馳せるのも良いかもしれない。
思い起こすのは、太宰治の『葉桜と魔笛』(1939年)という短編だ。それは「桜が散って、このように葉桜のころになれば、私は、きっと思い出します。――と、その老夫人は物語る」という一文から始まる。
後に老夫人となる姉が若かりしころ、病弱な妹がいた。ある日、姉が妹のタンスを整理したところ、男性からの手紙の束を発見する。手紙の最後の一通には、妹の病気を知ったので互いを忘れようと書かれていた。そこで姉は、筆跡をまねて励ましの手紙を妹に渡す。
「僕たち、さびしく無力なのだから、他になんにもできないのだから、せめて言葉だけでも、誠実こめてお贈りするのが、まことの、謙譲の美しい生きかたである、と僕はいまでは信じています」「あしたの晩の六時には、さっそく口笛、軍艦マアチ吹いてあげます。僕の口笛は、うまいですよ。いまのところ、それだけが、僕の力で、わけなくできる奉仕です」という一文をしたためて。
だが、妹はすべてを知っていた。今までの男性からの手紙は自分で書いたものだと打ち明け、誰との出会いもなしに死んでいく恐怖におののくのだった。2人が抱き合い涙を流すと、低く幽かに、口笛が葉桜の奥から聞こえてきた。それはちょうど、夕の六時のことだった。
「三日目」、妹は死の床につく。あまりにも早い死に医者は首をかしげるのだが、姉は「神さまは、在る。きっと、いる。私は、それを信じました」と独白するのだった。そして年老いた姉は、ひょっとしたらあの口笛は父のものかもしれない。だが、やはり神さまのお恵みではないか。「私は、そう信じて安心しておりたいのでございますけれども、どうも、年とって来ると、物慾が起り、信仰も薄らいでまいって、いけないと存じます」という言葉で、この作品は幕を閉じる。太宰は神の不在と同時に、一人ひとりの祈りを描くのである。
聖書は、十字架において徹底的にイエスの孤独を伝える。父なる神の不在という孤独。弟子たちや人々の無理解という孤独を。誰からも理解されないという人間の絶望を描くのだ。
人間は常に絶望に怯え生きている。この絶望を思い起こすと、目眩を覚えるかもしれない。高いところに立つと、転落する不安に駆られるように。朝になれば光が差すというのに、夜の闇を怖がるように。
この深淵、まことの闇の中、祈り続けるイエス・キリストの御姿がある。イエスは、ご自分の両隣に架けられた罪人のため、また自分を十字架に架けた人々のために祈られた。投げ捨てられた人々のために、夕暮れを恐れる人々のために。
愛は深ければ深いほど、誰かの苦しみを引き受けるものである。イエスの十字架の苦しみは、すべての人の苦しみを意味する。聖ボナヴェントゥラが言うように、自分の運命と他人の運命の区別がなくなればなくなるほど、愛は大きくなるのだ。
すると、私たちはこの十字架に、神の愛の輝きを見出すことができる。御子の十字架において、御父が苦しまないことがあろうか。十字架には父なる神の愛が秘められている。その愛によって、私たちを愛されるイエス・キリストの御姿がある。そして主イエスの愛の血の流れは聖餐や誰かの祈りを通して、私達の心と体の糧となり無数の花を咲かすのだ。
桜花は過ぎ、葉桜が目を楽しませる。新緑は落ち葉となり裸の枝となろうとも、変わらぬ雨と太陽と、夜と朝との繰り返しにより、新たな蕾の芽生えを私たちに伝える。祈りと共に、十字架と復活の日を歩んでいきたい。
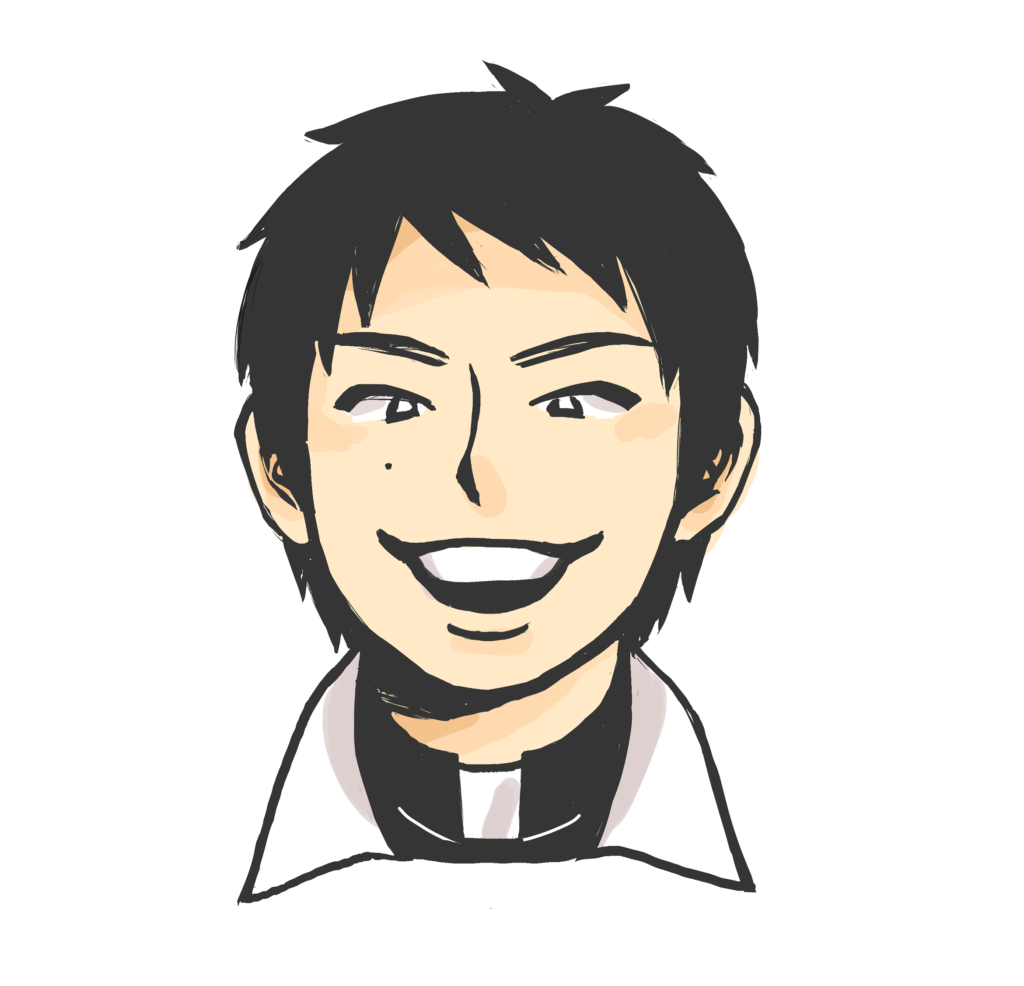
與賀田光嗣(神戸国際大学付属高等学校チャプレン)
よかた・こうし 1980年北海道生まれ。関西学院大学神学部、ウイリアムス神学館卒業。2010年司祭按手。神戸聖ミカエル教会、高知聖パウロ教会、立教英国学院チャプレンを経て現職。妻と1男1女の4人家族。






