15 忘れられない説教(1)
春が終わり、やがて迎えた暑さきびしい夏も行き、季節は秋に入った。
風が教会の庭の木を揺らし、葉を散らしていく。ひんやりとした空気が、夏の間火照(ほて)っていた会堂の隅々にまで行き渡り、私たちの気持ちもしんなりと落ち着かせてくれる。そんな穏やかな、恩寵(おんちょう)にも似た日々がつづいたある日。
しかしその朝は、厚い黒雲の広がる肌寒い日曜日だった。
窓の外に今にも降りだしそうな鉛色(なまりいろ)の空が広がっている。朝の10時半だというのに、会堂は電灯を点(つ)けなければならない暗さだった。礼拝が始まり、賛美歌が唱(うた)われ、先生が司会者と代わって講壇に立っていく。いつもながらの聖日の朝の風景。
私は膝(ひざ)の上の聖書に両手を載せ、ぼんやりと壇上を見上げていた。疲れと寝不足のためだっただろうか、身体が怠(だる)く、瞼(まぶた)も重く、どうしても説教に集中できない。
早く話が終わればいいなあ。
不謹慎にもそんな思いで、私は腕時計の針の進み具合をさっきから何度も確かめていた。
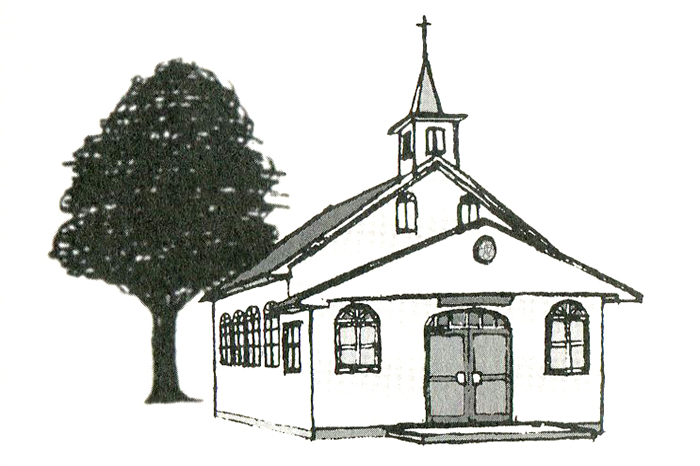
その朝の説教は新約聖書のマルコの福音書からであった。先生はその2章に出てくる「レビ」という人物について語っていた。
レビはユダヤ人でありながら、当時の権力者であるローマ人の手先となり、同胞のユダヤ人からローマに納める税金を取り立てる仕事をしていた。
取税人と呼ばれていた彼らは、税金をごまかして定額より多く相手から取り立て、その差額を自分の懐(ふところ)に入れるのが常であった。そのために裕福な暮らしはしていたが、ローマ人からは軽んじられて相手にされず、同胞のユダヤ人からは忌(い)み嫌われ、憎まれていた。
レビもほかの取税人同様に、ユダヤ人から村八分にされ、寂しい生活を送っていた。そんなレビのところに、ある日イエスがおいでになった。
イエスは道を通りながら、収税所に座っているレビをご覧になって、「わたしに従ってきなさい」といわれる。するとレビは立ち上がって、イエスに従った。
このあとイエスは、レビのような取税人や遊女など、罪人と呼ばれ、当時の社会から冷遇され、仲間はずれにされていた人々とともに、食事の席につかれる。たとえば男と女がともに食卓の席につくというのが、そのふたりが夫婦であることの証拠であるというように、この時代にあっては、一緒に食卓を囲むという行為は、互いの親密な間柄を公に示すことであった。
無論、これを見た世の人々が、このことに無関心でいられるわけがない。特に神への正統派の信仰者であることを誇るパリサイ人と呼ばれていた人たちが、このような世間の秩序を乱す行いについて、黙っているはずがなかった。
「なぜ、あなた方の先生は、取税人や罪人と一緒に食事をするのだ」
彼らはイエスの弟子たちにいった。
この時のイエスの答えは有名である。
「丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。わたしがきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである」
先生はあらましこんな話をしていった。それは馴染みのある聖書の箇所であり、今までもよく耳にした説教だった。
少しかすれた先生の声はつづく。
「レビは、こんなイエス様のお言葉を身近に聞き、どう思ったでしょうか。レビは、自分は罪人だと知っていたと思います。自分は正しくないと自覚していたと思います。人々に嫌われ、相手にされない寂しい生活……。でもレビは、それは自分にとっては仕方のない、あるいは当然の報いだと思っていたはずです。イエス様のお言葉を聞いて、レビはきっと今までの自分の仕事を悔いたでしょう。金のために権力者にへつらい、同胞をないがしろにしていた自分の生活、あるいは自分の生き方を悔いたでしょう。そして嫌われ者の自分をかばい、一緒に食卓の席についてくださったお方に、なんともいえない感謝を、愛を、感じたでしょう」
いつもと変わることのない淡々とした口調。咳(せき)まじりの枯れた声。しかしその眼には、情熱の火が炎々と燃えていた。どうしてもこれだけはという、神に召された人の心意気が感じられた。
私は疲れも眠気も忘れ、いつしか先生の話に引き込まれていた。(つづく)

