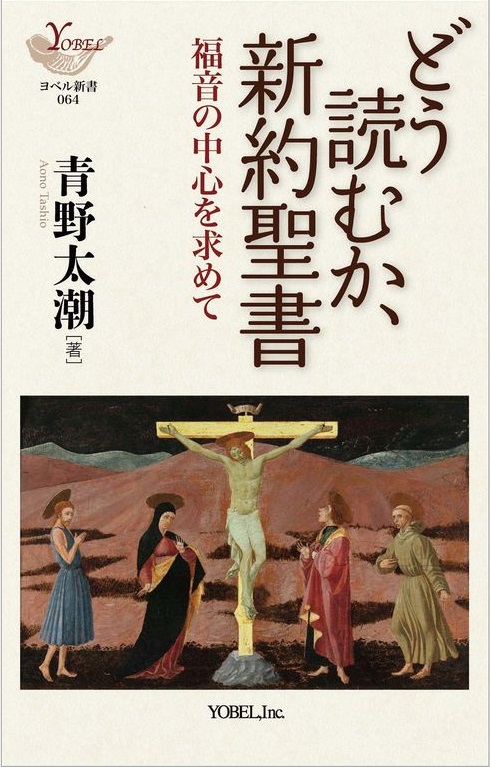
帯広告に、「処女降誕、贖罪、復活……。
本書は、キリスト教信仰を否定しない。むしろ、
例えば使徒信条に「処女マリアより生まれ」とあるのは、
さらに「
またキリスト教会は「イエスは肉体を伴って復活することで、
キリスト教は聖書を何度も読み直すことで、
(評者・廣石 望=立教大学教授)
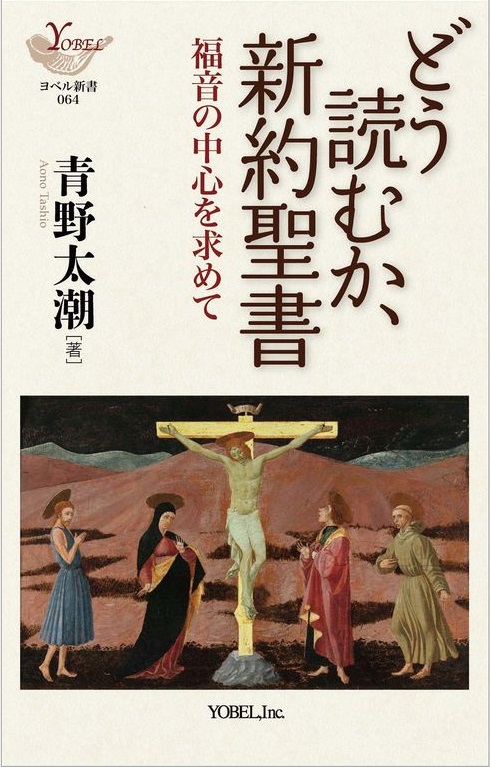
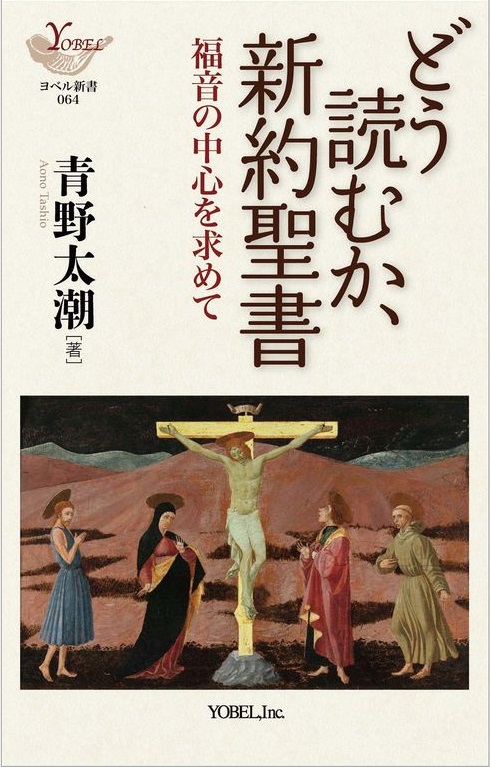
帯広告に、「処女降誕、贖罪、復活……。
本書は、キリスト教信仰を否定しない。むしろ、
例えば使徒信条に「処女マリアより生まれ」とあるのは、
さらに「
またキリスト教会は「イエスは肉体を伴って復活することで、
キリスト教は聖書を何度も読み直すことで、
(評者・廣石 望=立教大学教授)